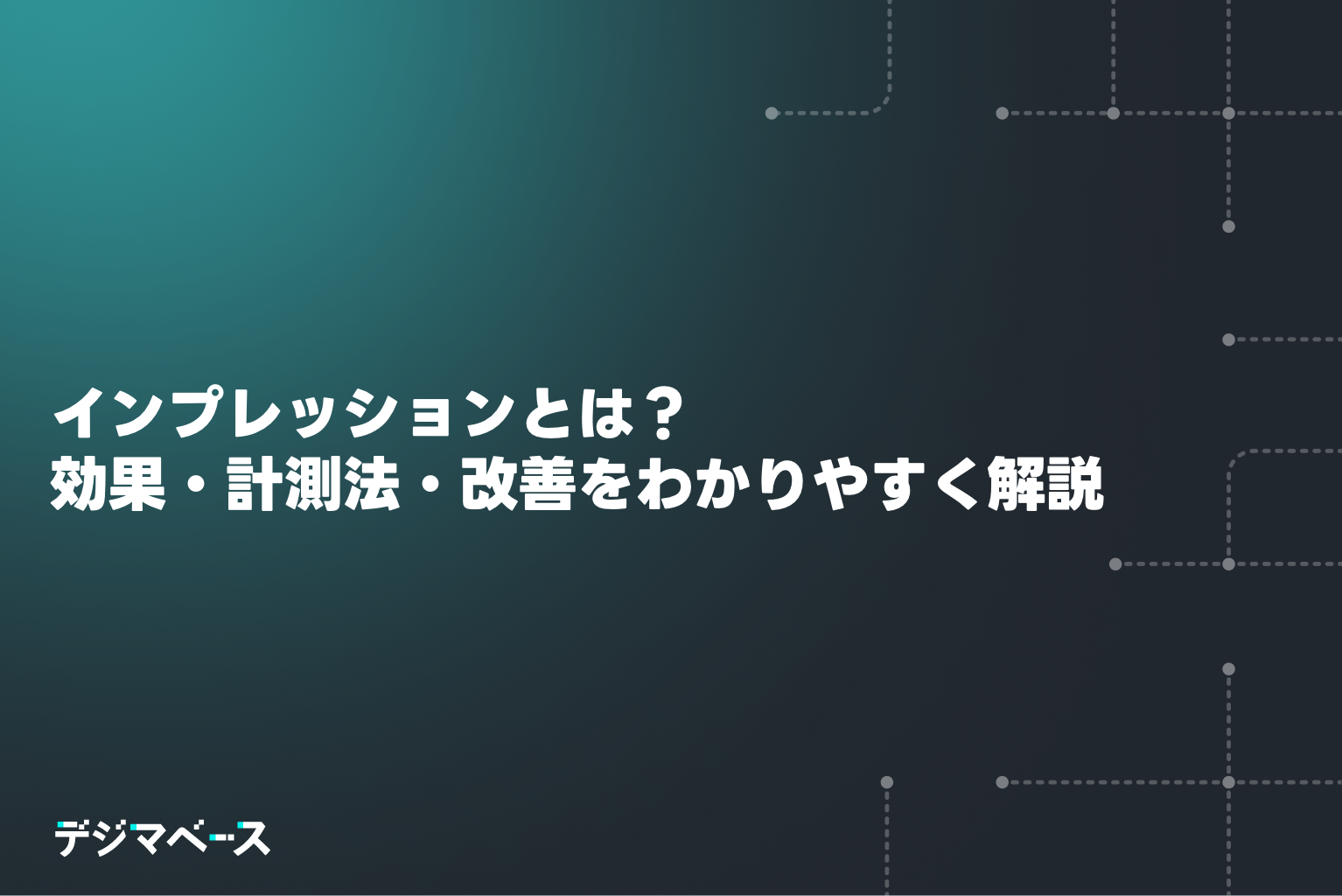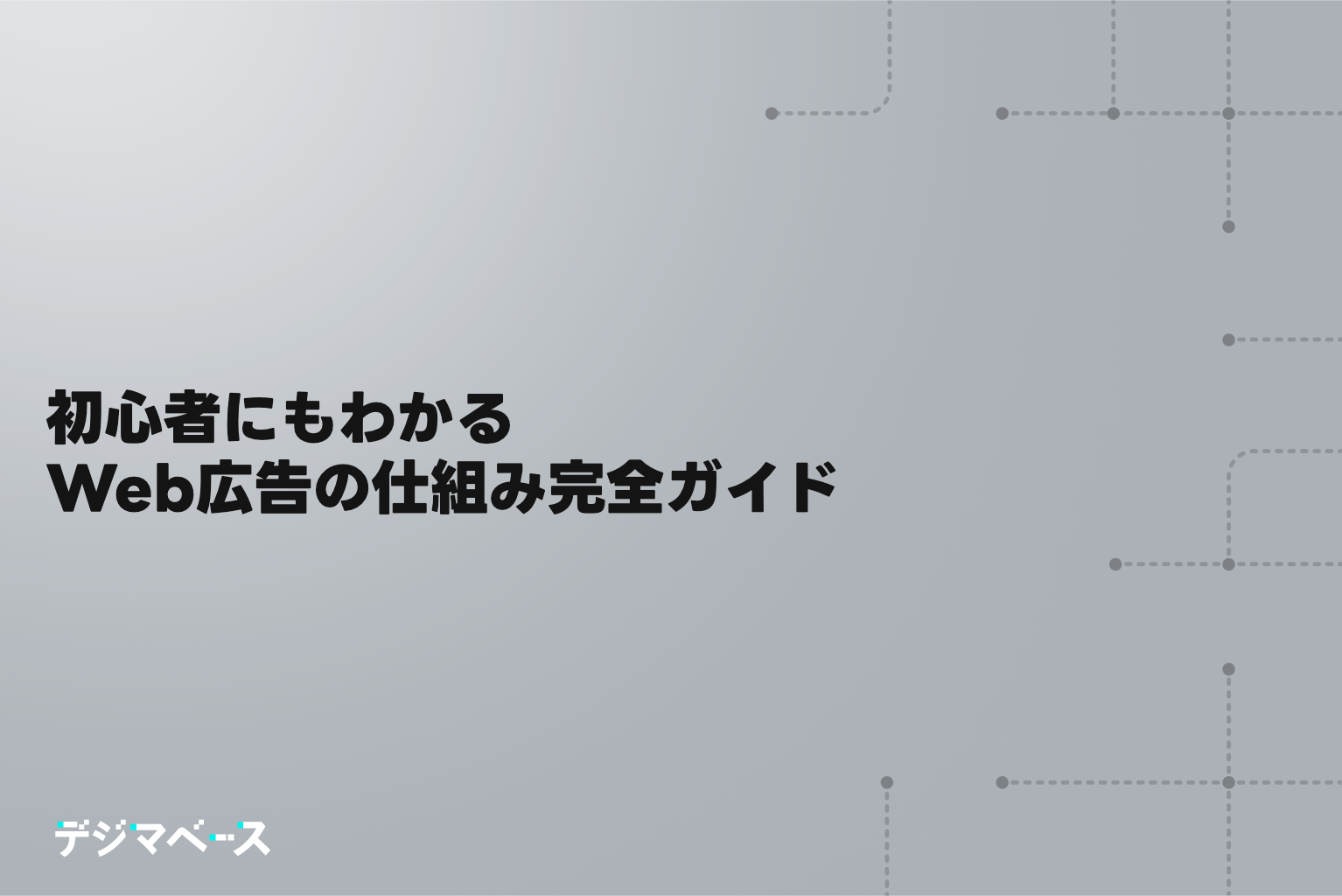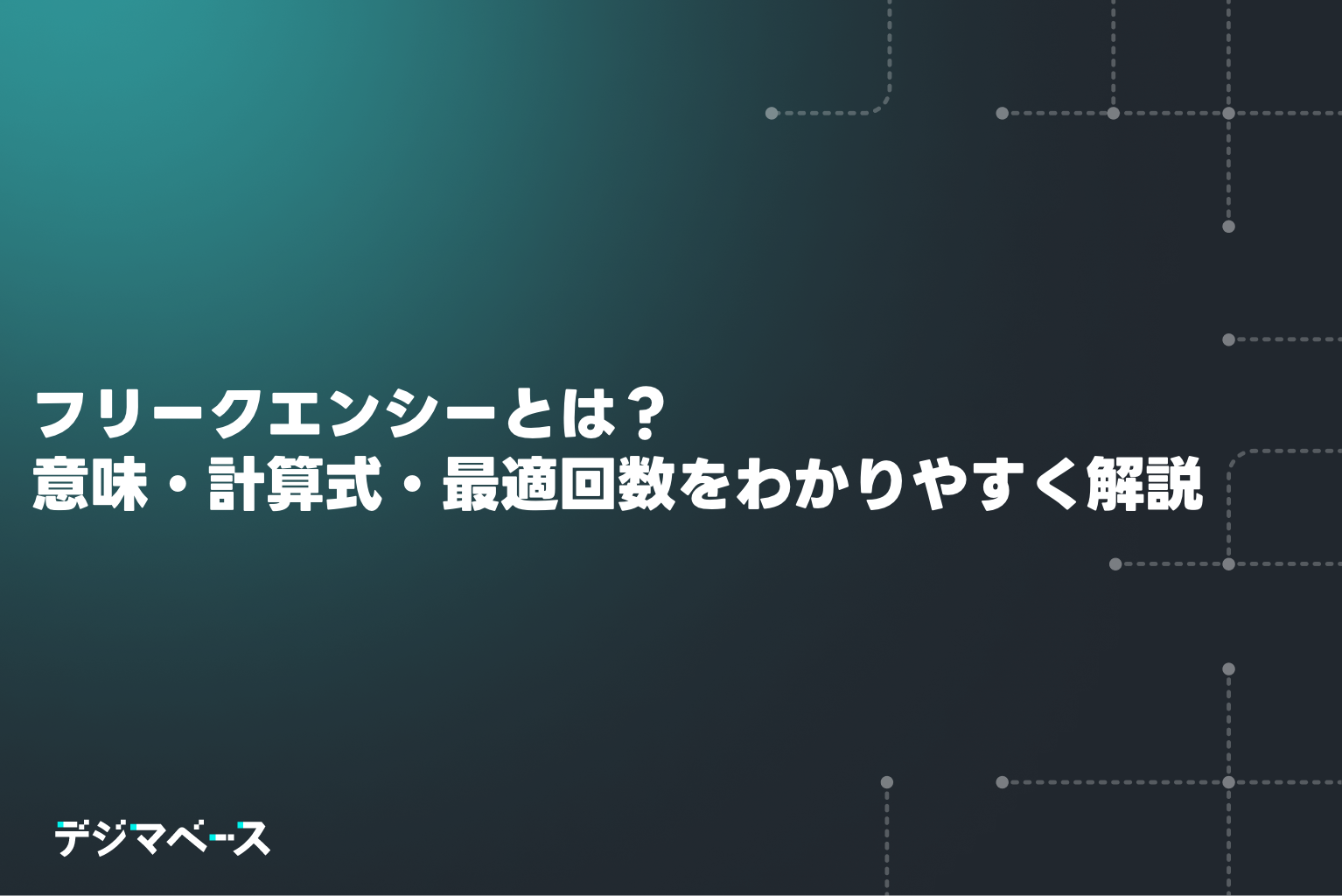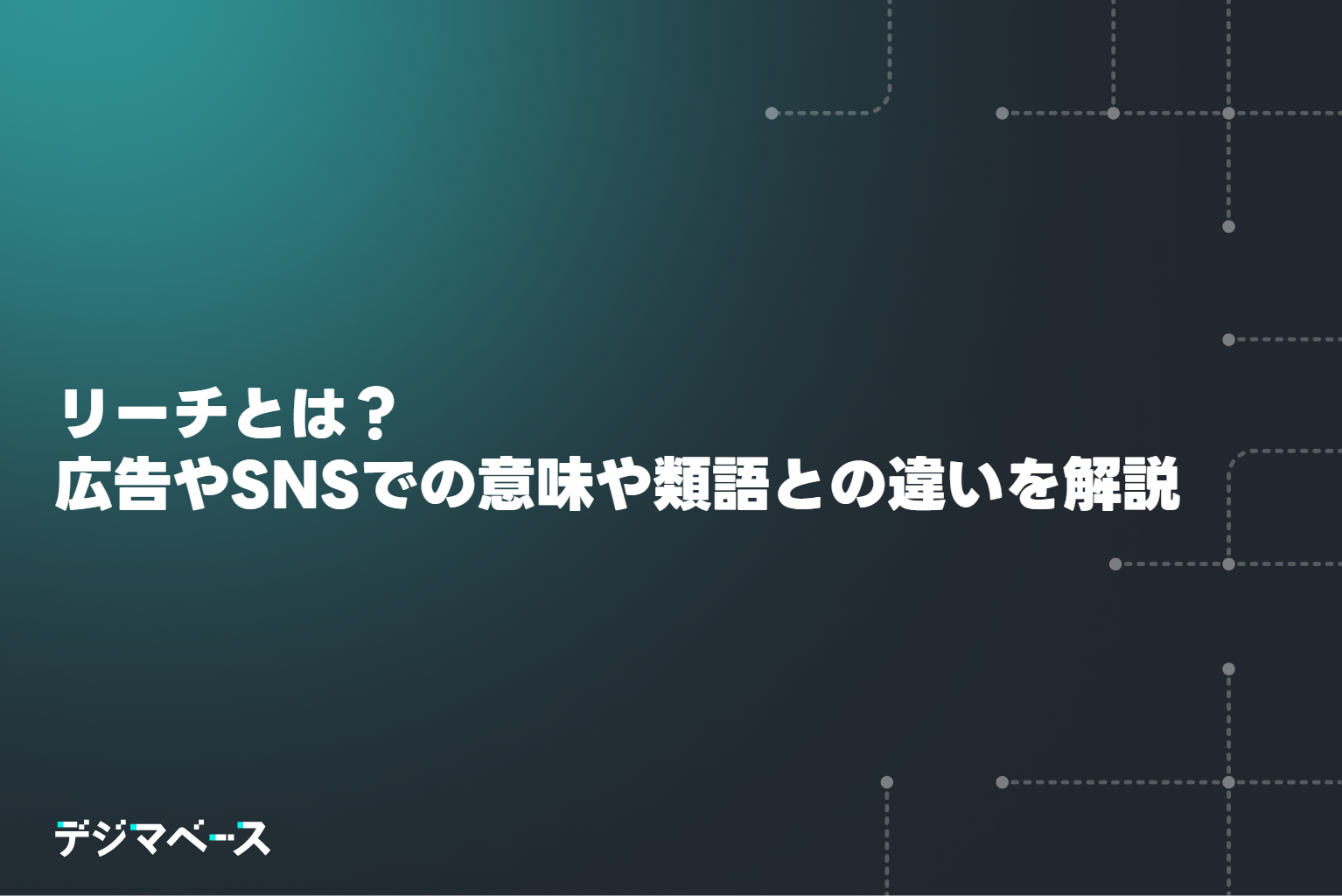
リーチとは? 広告やSNS、ビジネスでの意味や類語との違い
「リーチ」は広告やSNS分析などビジネスで欠かせない指標ですが、意味を誤解されやすい用語です。本記事では、マーケティングにおける役割や重要性などの基本から、類似用語との違い、効果的にリーチを増やす方法までを解説します。
リーチとは?
リーチとは、広告やコンテンツが実際に届いたユーザーの数を表す指標です。例えば、ある広告を配信した場合に1,000回表示されても、実際に表示を見たのが500人であればリーチは500になります。
類似指標にインプレッションがありますが、リーチは、同一ユーザーが何度表示を見ても1人としてカウントされます。そのため「どれだけの人々に情報を届けられたか」を判断する指標として活用されます。
広告キャンペーンやSNS運用でリーチを把握することで、商品の認知向上施策を効率的に進められます。
各媒体におけるリーチの定義
各媒体ごとに異なるリーチの意味や数え方を表で紹介します。何が違うのかを知っておくことで、施策における誤解を防げます。
| 媒体 | 定義 | 数え方の具体例 |
|---|---|---|
| Google広告(Google Ads) | 広告が表示されたユーザーの総数。デバイスやサイトをまたいで集計 | 同一ユーザーがPCで2回・スマートフォンで1回見てもリーチ=1、インプレッション=3 |
| Yahoo!広告 | 指定期間内でビューアブルインプレッションが発生したユニークユーザー数 | 同一人物がPCで1回+スマートフォンで1回視認可能表示 → 端末ごとにカウントされ合算リーチ=2、インプレッション=2 |
| LINE広告(LINE広告ネットワーク) | 広告を100%表示したユニークユーザー数 | Aさんに2回、Bさん1回、Cさん1回の100%表示 → リーチ=3、インプレッション=4 |
| Meta広告(Facebook / Instagram) | 広告を見たユニークアカウント数 | 1アカウントが10回見てもリーチ=1。10アカウントが各1回ならリーチ=10 |
| TikTok広告 | 広告に1回以上接触したユニークアカウント数 | 100アカウントに合計300回再生 → リーチ=100、インプレッション=300 |
リーチが重要な理由
こちらでは、Web広告やSNSにおいて、なぜリーチが重要なのかを5つのポイントから解説します。
- 認知を拡大できる
- 拡散されやすくなる
- 口コミやUGCが生まれやすくなる
- 指名検索が増え、サイト流入が増える
- 売上の母数を大きくできる
認知を拡大できる
リーチを拡大することで、まだ企業や商品を知らない潜在層に情報を届けることができます。特に新商品やサービスをローンチ(発売・提供開始)する際には、まず多くの人に存在を知ってもらうことが重要です。
- 潜在顧客に広く届けることでブランド認知が高まる
- 新商品の市場投入時の初速を上げられる
- 口コミやSNSでの話題化につながりやすくなる
このように、リーチが拡大することで「存在を知ってもらう」という最初の成果につなげられるのです。
拡散されやすくなる
SNS投稿はシェアによって、さらに多くの人にコンテンツを届けられます。つまり、リーチが大きいほど雪だるま式に拡散の機会が増えます。
特に話題性のあるコンテンツや時事性のある投稿は、さらに大きなリーチを獲得しやすくなります。
口コミやUGCが生まれやすくなる
リーチが広がることで多くの人が投稿に触れ、それに対して感想や体験をシェアし、企業や商品の信頼性向上につながります。
特にレビューや動画、ブログ投稿などのユーザー生成コンテンツ(UGC)は、広告よりも信頼されやすく、購買意欲を高める役割を果たします。
リーチが大きければ、その分だけ口コミやUGCが生まれる可能性が高くなるため、マーケティング戦略においてリーチの拡大は重要な要素といえます。
指名検索が増え、サイト流入が増える
リーチの増加は指名検索、つまり「社名やブランド名で検索される頻度」を高める効果もあります。多くの人に商品やサービスに関する投稿が届くと、自然と気になった人が会社名や商品名で検索するようになり、それが検索エンジン経由での流入増加につながるためです。
特に指名検索を行うユーザーは購入意欲が高いため、CVR(コンバージョン率)の上昇にも影響します。リーチ拡大は単純な露出効果にとどまらず、成果につながりやすい検索行動の増加という点で、取り組む価値のある施策です。
売上げの母数を大きくできる
売上は「認知→検討→購買」という流れを経て生まれます。そのため、最初の接点となるリーチが増えることは、最終的な売上の母数を大きくする点で重要です。
例えば、リーチが10万人に広がれば、そのうち1%が反応するだけで1,000人の顧客を獲得できます。一方で、リーチが5万人にとどまる場合、同じ1%の反応率でも得られる顧客は500人に減ってしまいます。このように、反応率が同じでも、リーチの大きさによって成果は大きく変わるのです。
だからこそ、広告で効率的に売上を伸ばすには、クリック率や成約率だけでなく「どれだけ多くの人に届けられたか」を意識する必要があります。
リーチと混同されやすい類似用語との違い
この章では、リーチと混同されやすい類似用語との違いを解説します。それぞれの言葉の意味を理解することで、施策や会議における認識違いを防げます。
インプレッションとの違い
リーチとインプレッションは同じ文脈で語られることが多いものの、意味は異なります。リーチは広告や投稿が「何人に届いたか」、インプレッションは「何回表示されたか」を示す指標です。例えば、1人のユーザーに同じ広告が5回表示された場合、リーチは1、インプレッションは5になります。
広告やSNSの効果測定では両者を組み合わせて捉え、リーチで認知の広がりを、インプレッションで接触回数の多さを評価します。
【関連記事】インプレッションとは?効果・計測方法・改善策をわかりやすく解説
フリークエンシーとの違い
フリークエンシーは「1人あたりの表示回数」を示します。
例えば、インプレッションが1,000、リーチが500であれば、フリークエンシーは2(1,000÷500)となります。つまりユーザー1名あたり平均2回の広告に接触したことを意味します。
フリークエンシーは、値が高すぎると同じユーザーに繰り返し配信されて効果が薄れ、いわゆる「広告疲れ」を招くおそれがあります。逆に低すぎると認知が十分に浸透せず、行動や購買につながりにくくなります。
効果測定では、リーチで広がりを、フリークエンシーで接触の深さを確認し、両者のバランスを適切に管理することが重要です。
【関連記事】フリークエンシーとは?意味・計算式・最適回数をわかりやすく解説
エンゲージメントとの違い
エンゲージメントは「いいね」「コメント」「シェア」「クリック」など、ユーザーの自発的な行動を示します。
そのため、リーチが大きくてもエンゲージメントが低い場合は、認知は広がっていても内容への関心が高くないと解釈できます。逆にリーチが小さくてもエンゲージメントが高い場合は、ターゲット層に強く響いているといえます。
マーケティングの評価では、どちらか一方に偏らず、両指標の関係性を踏まえて判断することが重要です。
PVとの違い
リーチが主に広告やSNSにおいて「何人に届いたか」を見る指標であることに対して、PV(ページビュー)は、Webサイト上で「ページが何回表示されたか」を示す指標です。
サイト分析では、訪問したユーザー数とPV数を分けて分析します。例えば、1人のユーザーが同じ記事を3回閲覧した場合、ユーザー数は1、PVは3としてカウントされます。
この区別を押さえていないと、実際の訪問者数以上に、サイトが見られていると誤解してしまいます。そのため訪問したユーザー数とPV数は分けて考えることが重要です。
セッションとの違い
「セッション」はPVと似ていますが、数え方が異なります。セッションは、ユーザーがサイトで行う一連の行動のまとまりで、30分間操作がないと終了します。その後に再度ページを閲覧するなどの行動が起きた時点で新しいセッションが開始されます。
例えば、1人のユーザーが30分以内に3ページを見た場合はPV=3、セッション=1です。1度の訪問のまま30分を過ぎても行動がなければセッションは増えません。
PVとセッションを組み合わせて見ることで、1回の訪問でどれくらい深くサイトを利用したかを把握できます。たとえば、平均PV / セッションが高いほど、関心が高くサイトが閲覧されている可能性があります。
リーチの増やし方
この章では、Web広告やSNSを中心にリーチを増やす具体的な方法を解説します。
Web広告でのリーチの増やし方
Web広告で成果を上げるためには、狙ったターゲットに広告を届けるだけでなく、より多くの人にリーチさせるという視点も重要です。ここではターゲティングや配信方法の工夫、クリエイティブ改善など、実務に直結する施策を解説します。
- ターゲティングの範囲を広げる
- 配信方法や配信面を増やす
- リーチ重視のキャンペーンに切り替える
- 配信日時や頻度を管理する
- クリエイティブの質を高める
ターゲティングの範囲を広げる
広告のリーチを伸ばすには、狙うユーザー層を広げることが有効です。例えば、年齢や性別を限定せずに幅広く設定したり、興味関心のカテゴリを複数追加したりすることで、潜在的な顧客層にも広告が届きやすくなります。また、既存顧客に似た属性のユーザーをAIが見つけてくれるターゲティング拡張機能を活用するのも有効です。
- 地域ターゲティングを拡大する
- 年齢・性別の制限を緩める
- 興味関心カテゴリを広く設定する
- ターゲティング拡張機能を利用する
配信方法や配信面を増やす
広告媒体ごとに用意されている配信面や配信フォーマットを積極的に利用することで、リーチを拡大できます。
例えばGoogle 広告ではディスプレイネットワークやYouTubeを組み合わせ、Meta広告ではFacebook・Instagram両方を活用するのが効果的です。さらにYahoo!広告では検索広告とディスプレイ広告を併用することで、幅広いユーザー層にアプローチできます。
配信方法を多角化すると、ユーザーの広告接触機会が広がります。
リーチ重視のキャンペーンに切り替える
広告媒体ごとに用意されたキャンペーンや戦略のタイプから「リーチ重視」のものを選ぶことで、配信最適化がクリックやコンバージョンではなく、より多くの人に見られることにフォーカスされます。主要な広告媒体におけるリーチ拡大を目的としたキャンペーンは次の通りです。
| プラットフォーム | キャンペーン名 |
|---|---|
| Google 広告(動画) | Video reach campaigns |
| Google 広告(ディスプレイ) | ブランド認知とリーチ(Brand awareness & reach) |
| Yahoo!広告(ディスプレイ広告・運用型) | ブランド認知 |
| LINE広告 | リーチ |
| Meta 広告(Facebook / Instagram) | 認知(Awareness)キャンペーン(※パフォーマンス目標:Reach) |
| TikTok 広告 | Reach |
配信日時や頻度を管理する
Web広告では、設定した広告の配信対象の中で予算を使い切るように配信します。そのため対象の人数が少ないほど広告を見てもらえる相手が限られ、同じ人に何度も広告が表示されやすく、新規に広告を目にする人(リーチ)が増えにくくなります。
これを防ぐためには、配信日時を分散して特定の時間帯に集中して広告が配信されることを避ける、またフリークエンシーキャップ(同一ユーザーへの表示上限回数)を設定するなどを考える必要があります。
また併せて配信対象や配信先、期間、入札戦略、予算を見直すことで、広告の無駄を抑えつつ、新規リーチを増やせます。
クリエイティブの質を高める
広告を配信するターゲットを拡げても、広告クリエイティブの内容が響かなければリーチは伸び悩みます。というのも、広告プラットフォームでは、クリック率の高いクリエイティブは、配信されやすくなる仕組みがあるためです。
そのため、訴求ポイントを明確にした上で、ターゲットが思わず目を止めるキャッチコピーやクリエイティブを設定することが大切です。
SNSのリーチの増やし方
SNSのリーチを増やすには、投稿内容やタイミング、フォロワーとの関係性など、多面的な工夫が求められます。ここでは日々の運用で実践できる具体的なポイントを解説します。
- 投稿頻度を増やす
- 最適な時間に投稿する
- ハッシュタグを活用する
- クリエイティブの質を高める
- フォロワーと交流する
投稿頻度を増やす
投稿回数が増えるほど、SNSアルゴリズム上で露出機会が増えやすくなります。毎日投稿できなくても、週に複数回、継続的に発信することで、フォロワー外のユーザーにも表示されやすくなります。
ただし、各SNSのプラットフォームはエンゲージメントも評価するため、質を犠牲にして無理に量を増やすと逆効果となるので、バランスを意識することが重要です。
最適な時間に投稿する
投稿が見られやすいのは、フォロワーがアクティブな時間帯です。通勤前後や昼休み、夜のリラックスタイムなど一般的に反応が高まりやすい時間を試し、インサイトをもとに最適な時刻を見極めます。
曜日ごとの差や季節による変化も踏まえて計画を見直すと、より多くの人に投稿が届きやすくなり、自然とリーチ拡大につながります。
ハッシュタグを活用する
ハッシュタグは、新規ユーザーに投稿を見つけてもらう有効な手段です。関連性の高いものを少数選び、ブランドやテーマ、トレンドを組み合わせると効果的に露出を増やせます。
投稿後は到達数やプロフィール遷移の数値を確認し、タグを入れ替えて改善するのが大切です。ただし、無関係なタグや過剰な数の利用は逆効果になることがあるため注意が必要です。
クリエイティブの質を高める
広告と同じく、SNS投稿も内容が響かなければリーチは伸びません。冒頭の画像や最初の数秒で興味を引き、1投稿につき伝えたいことを1つに絞って明確に伝えましょう。
推奨サイズや尺を守り、サムネイルやコピーはABテストで改善を重ねることが重要です。さらにデザインやコピーを定期的に見直して新鮮さを保つことで、より多くの人に表示されやすくなります。
フォロワーと交流する
フォロワーとの交流はリーチ拡大につながります。コメントやDMに丁寧に返信し、質問や投票など参加しやすい仕掛けを用いることで、会話が増え、アルゴリズム上も投稿が表示されやすくなります。
反応を無理に求めず、役立つ情報や気軽に参加できる話題を提供することが大切です。こうした小さなやり取りの積み重ねが信頼を生み、新規ユーザーにも届きやすくなります。