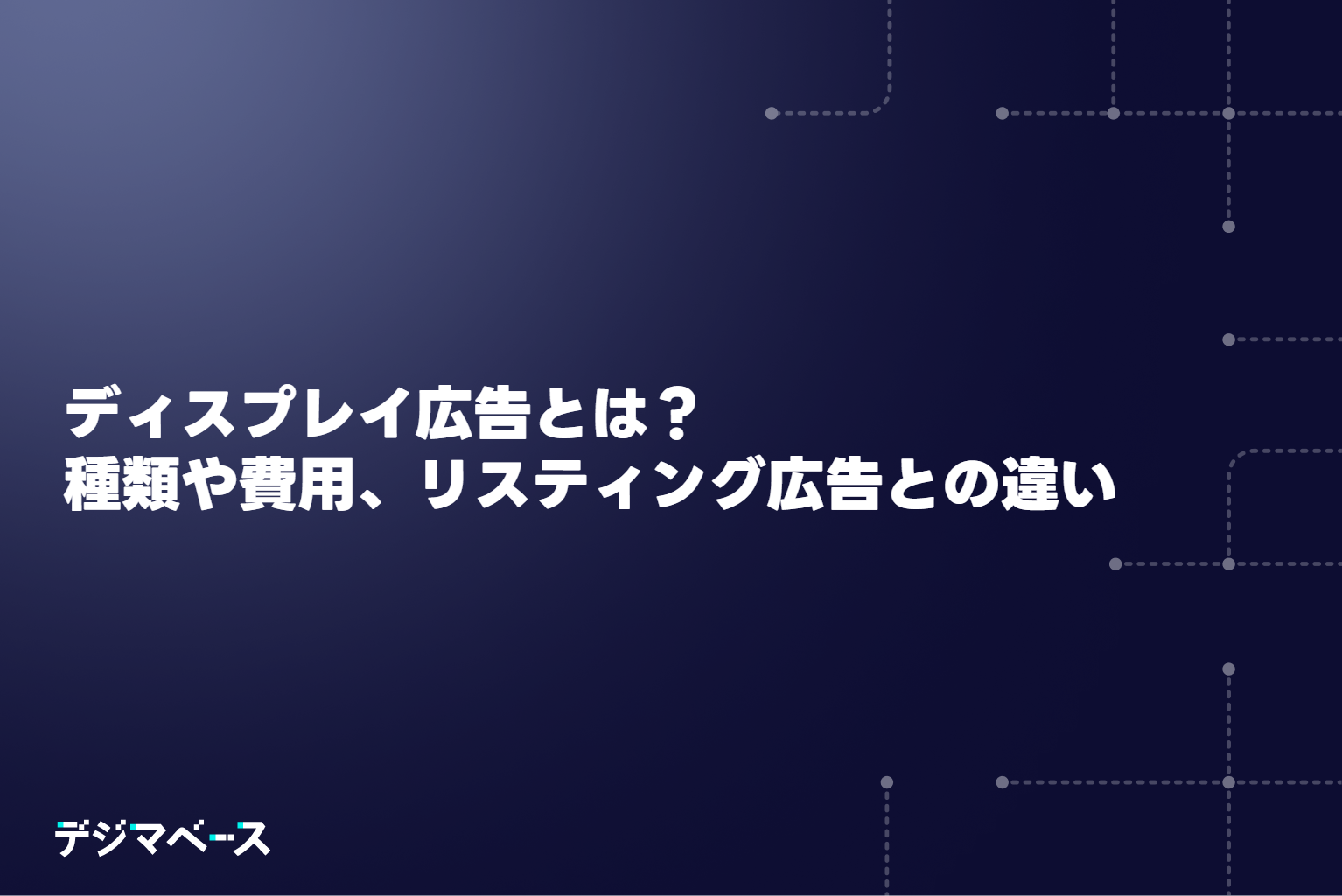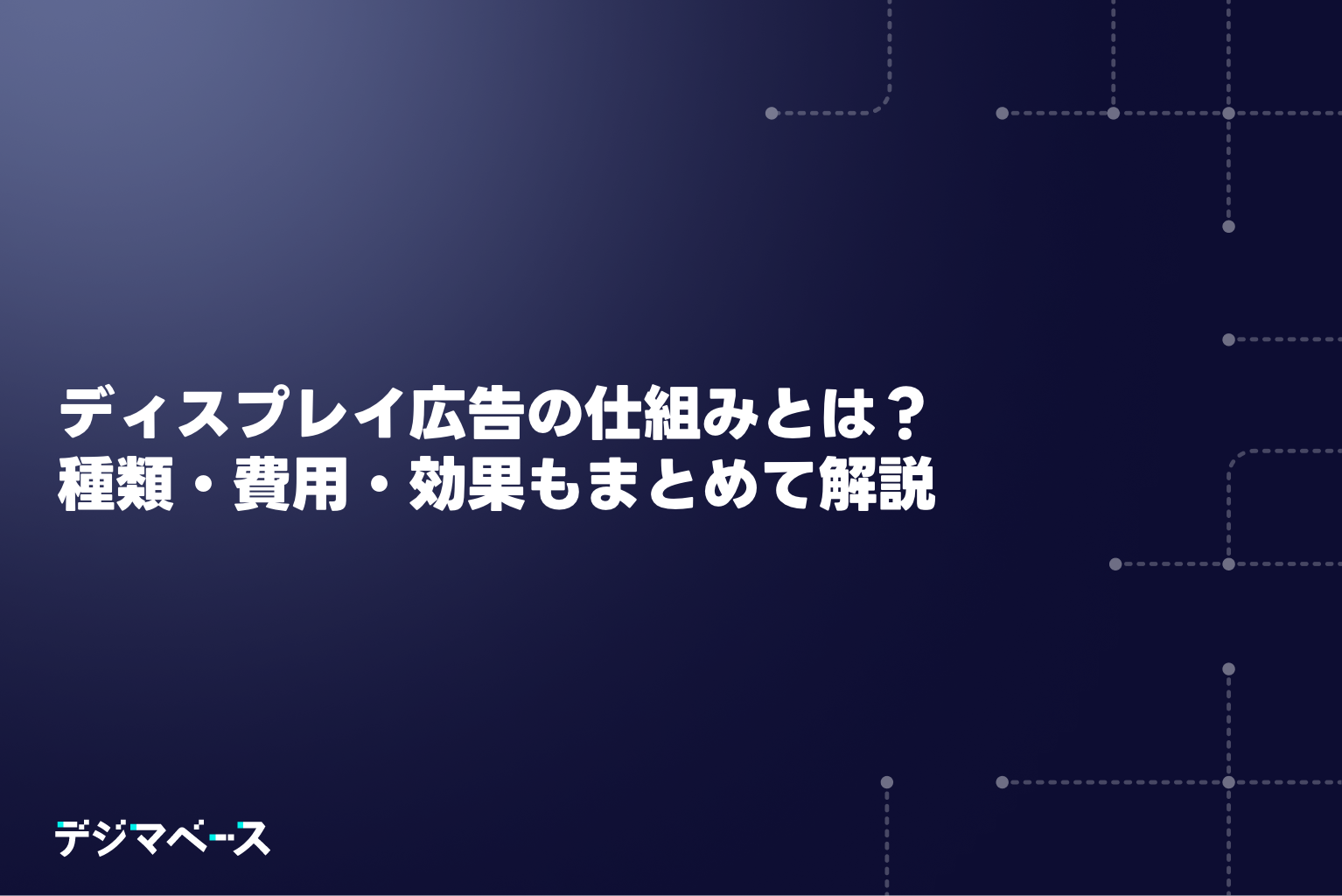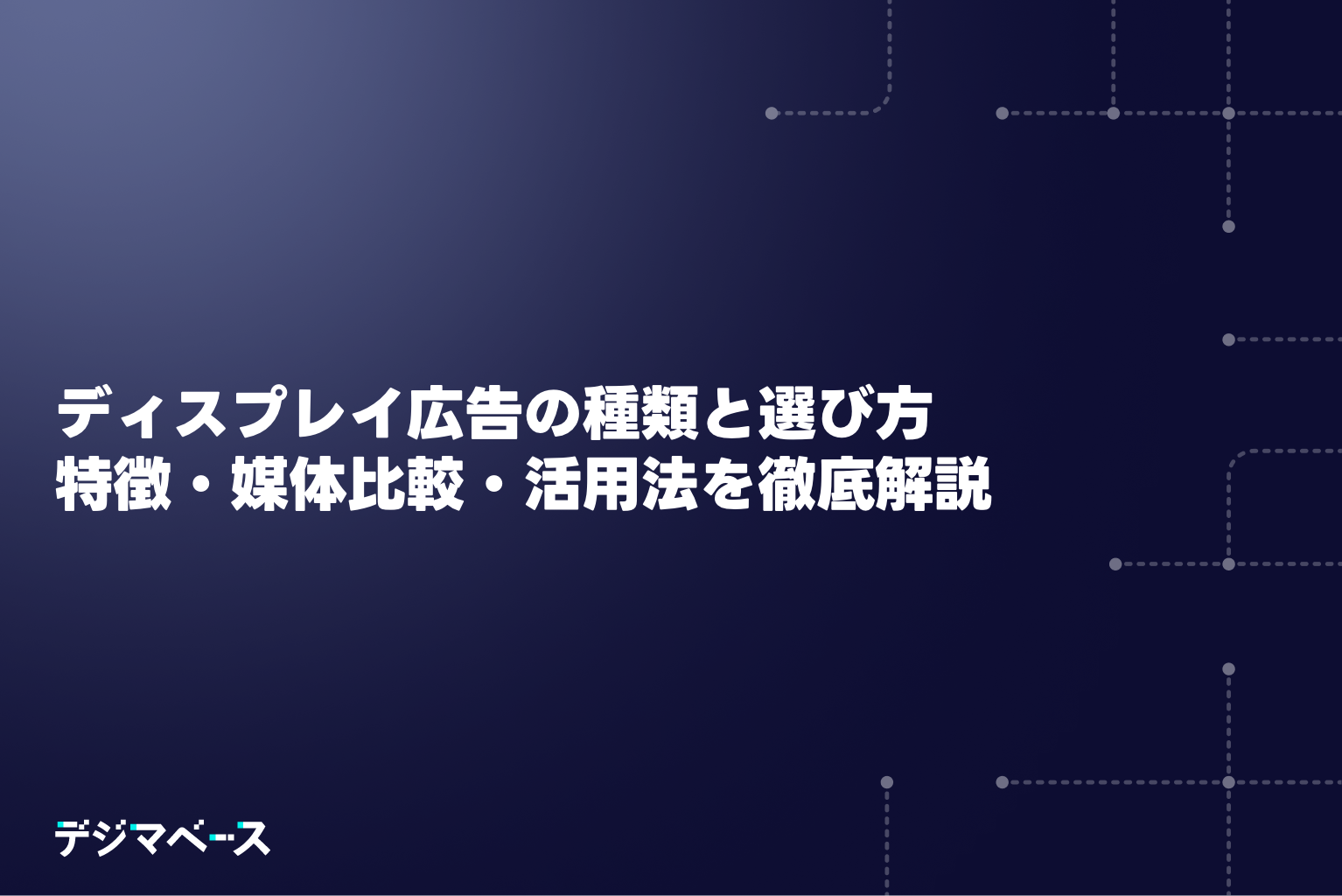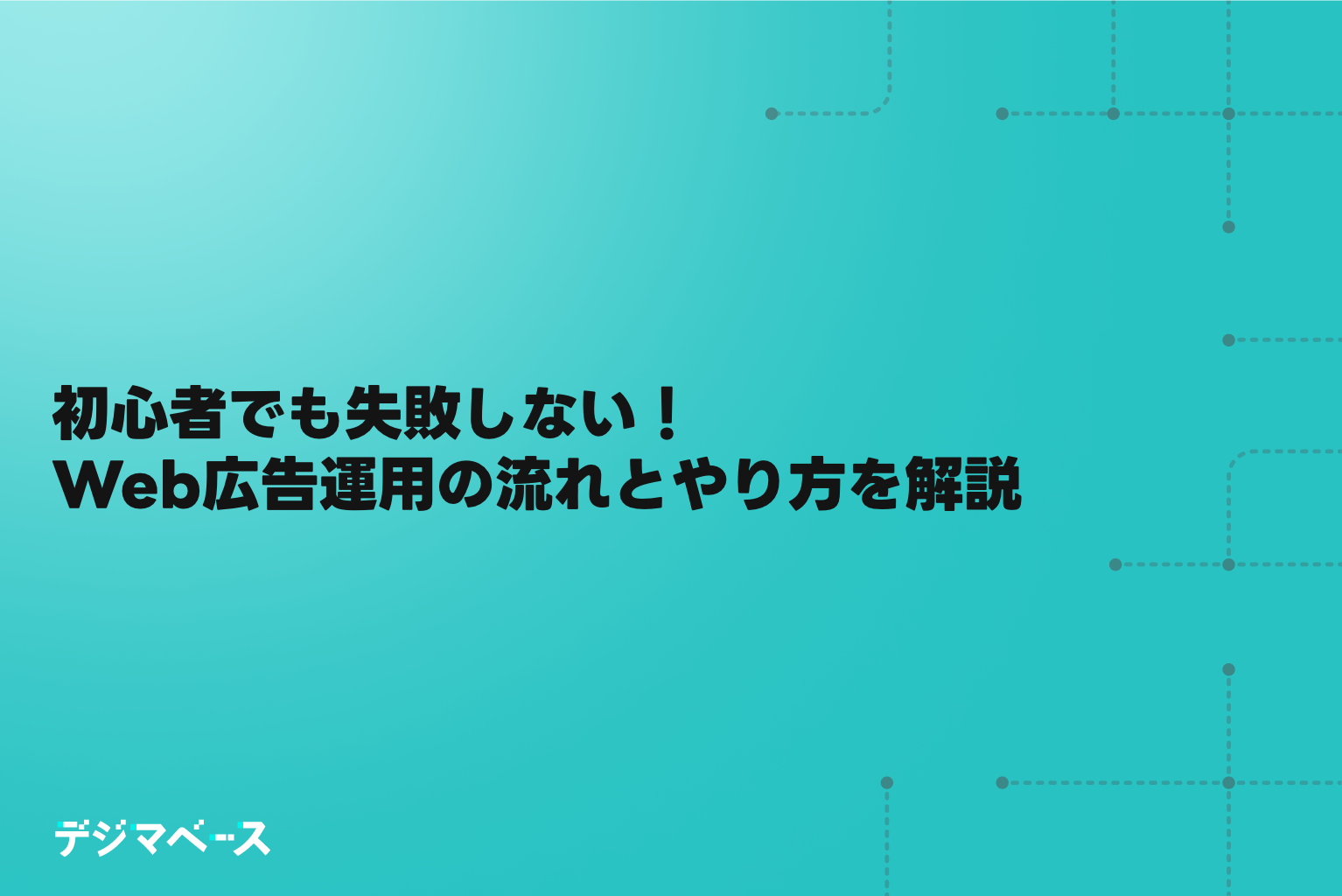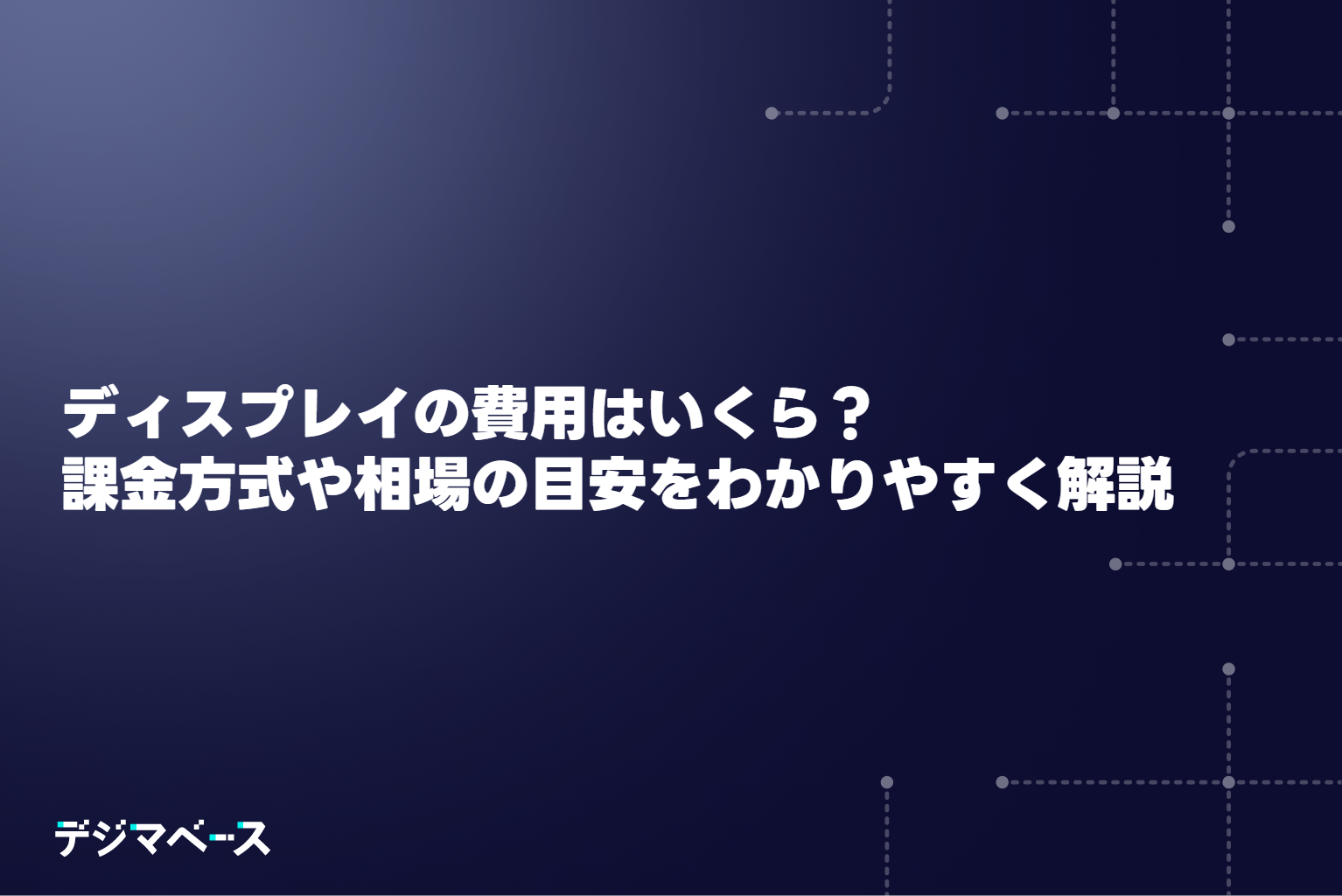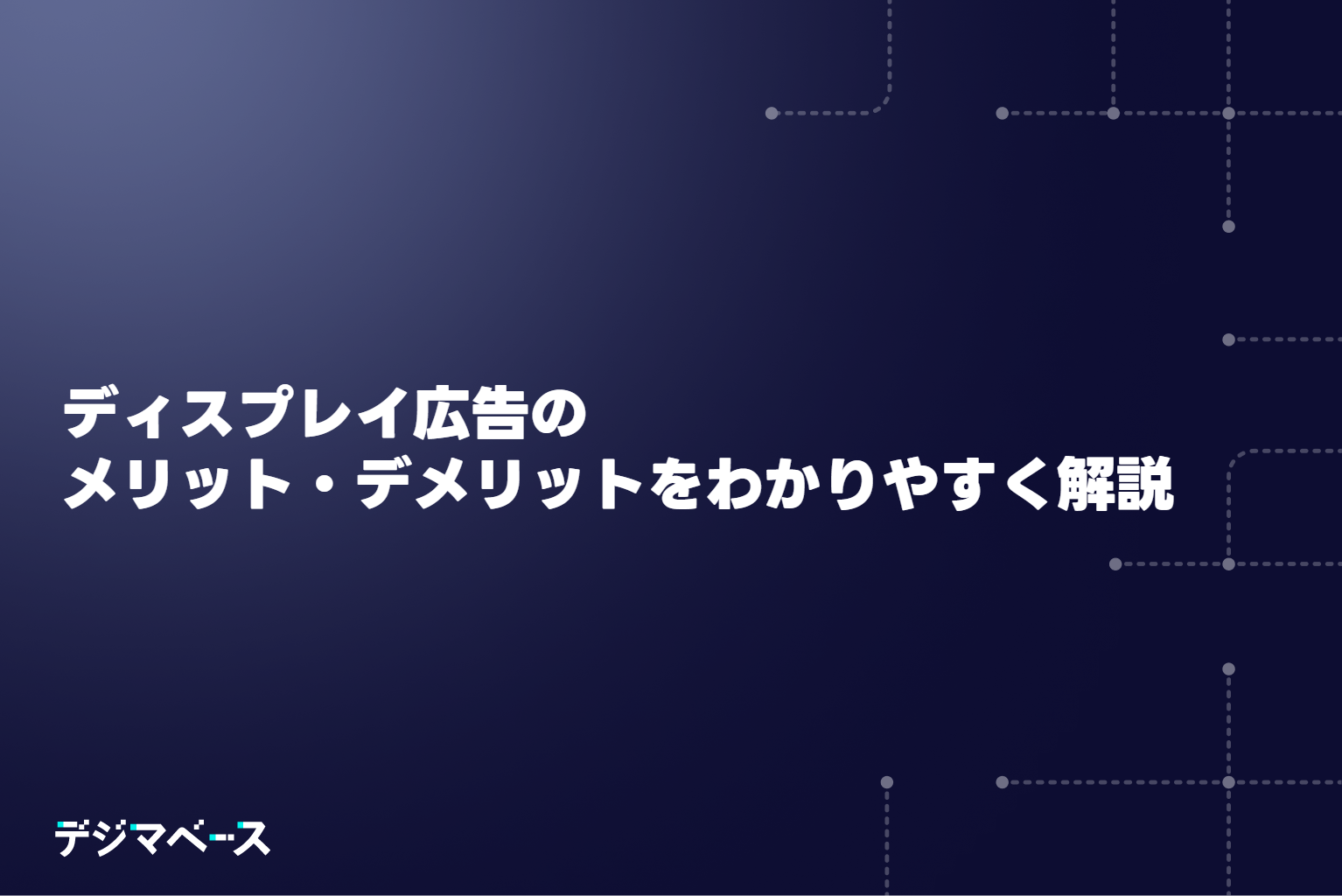
ディスプレイ広告のメリット・デメリットをわかりやすく解説
ディスプレイ広告は企業の認知拡大やブランディングに効果的な一方で、運用の難しさやリスクも伴います。本記事ではメリット・デメリットを整理し、具体的な事例や活用法を紹介。広告戦略に役立つ実践的な知識をわかりやすく解説します。
ディスプレイ広告とは?
ディスプレイ広告とは、Webサイトやアプリ上に表示されるバナーや動画などの広告を指す言葉です。検索結果画面にテキスト形式で表示される検索連動型(リスティング)広告と異なり、ユーザーが能動的に検索していない段階でも広告を届けられる点が特徴です。
【関連記事】ディスプレイ広告とは? 種類や費用、リスティング広告との違いを解説
ディスプレイ広告のメリット
ディスプレイ広告のメリットは、潜在層へのリーチ、視覚的訴求、リマーケティングなどさまざまです。本章では、5つメリットを具体的に解説します。
- 潜在層にアプローチできる
- 画像や動画で訴求できる
- リマーケティングできる
- CPCが比較的低くなる
- 認知獲得やブランディングにつながる
潜在層にアプローチできる
メリットの1つ目は、まだ商品やサービスを積極的に探していない潜在層にアプローチできることです。
リスティング広告の場合、検索キーワードを入力するユーザーに限定されますが、ディスプレイ広告では行動履歴や興味関心、閲覧ページなどのデータをもとに、自社商品に関連性の高いユーザーに接触できます。
これにより、購買プロセスの早い段階でブランドや商品を認知してもらえ、最終的に購買につながる確率を高めます。特に新商品や新サービスを市場に導入する際には、潜在層に早い段階で接触できることが利点となり、競合との差別化にも効果を発揮します。
画像や動画で訴求できる
2つ目は、テキストだけでなく画像や動画を用いて視覚的に訴求できることです。ユーザーの視覚に訴えかけることで、直感的に商品の特徴や魅力を理解されやすく、記憶への定着もしやすくなります。
また、動画広告ではストーリーテリングが可能なため、ブランドの世界観や利用シーンを具体的に伝えられる点も魅力です。例えば、ファッションブランドであればコーディネート例を見せたり、食品業界であれば料理シーンの動画を活用したりすることで、購買意欲を高められます。
テキスト主体の広告と比べると、ユーザーの印象に残りやすく、SNSでの共有や口コミにもつながりやすい点がメリットです。
リマーケティングできる
3つ目は、過去に自社サイトを訪問したものの購買やお問い合わせに至らなかったユーザーに対し、再度アプローチできる「リマーケティング」を実施できることです。例えば、カートに商品を入れたまま離脱したユーザーに関連商品の広告を表示することで、購買完了率を高められます。
また、特定の商品ページを何度も閲覧しているユーザーには、その商品のお得なキャンペーンを訴求するなど、パーソナライズされた広告配信ができます。これにより、広告費を効率よく活用しつつ、CVR(コンバージョン率)の向上を実現できる点が魅力です。
【関連記事】初心者マーケター必見!2025年版リターゲティング広告の仕組みと活用法
CPCが比較的低くなる
4つ目は、CPC(クリック単価)が比較的低い傾向にあることです。一般に、検索連動型(リスティング)広告は検索意図の強いユーザーが対象となるため競争が激しく、クリック単価が高騰しやすい傾向があります。一方、ディスプレイ広告はより広範なユーザー層への配信が可能であるため、競合度が相対的に低く、クリック単価を抑えやすいのです。
特に中長期的なマーケティング戦略においては、低単価で多くのユーザーに接触できることが重要な意味を持ちます。また、広告費が限られている中小企業でも、比較的リーズナブルに広告配信を行いながら成果を積み重ねることができます。
認知獲得やブランディングにつながる
最後は、認知獲得やブランディングにも効果的である点です。ユーザーが商品やサービスを知るきっかけを提供し、ブランドイメージを潜在層に広く浸透させることができます。
企業ロゴやブランドカラーを一貫して使用することで、視覚的に認識されやすくなり、長期的には顧客の信頼感やブランド好意度を高めることにつながります。特に大規模なキャンペーンやテレビCMと組み合わせた「マルチチャネル戦略」において、オンライン接触点としてディスプレイ広告を併用すると、広告全体の波及効果を強化できる点が強みです。
ディスプレイ広告のデメリット
ディスプレイ広告には多くのメリットがある一方で、即効性の低さや効果検証の難しさなどのデメリットが存在します。それぞれ具体的に見ていきましょう。
- 即時的な効果につながりにくい
- 効果検証が容易ではない
- 広告費の消化が比較的速い
- 配信面ごとにクリエイティブ制作が必要になる
- ブランド毀損につながる可能性がある
即時的な効果につながりにくい
ディスプレイ広告は、検索キーワードに基づいて配信されるリスティング広告と比べて、ユーザーが商品やサービスを必要としているタイミングをとらえることが難しいという特徴があります。
つまり、必ずしも「今すぐ買いたい」人に届くわけではなく、購買意欲が低い潜在層への露出が中心となるため、クリックやコンバージョン(CV)といった即時的な成果につながりにくいのです。
そのため「急いで売上を伸ばしたい」といった短期の施策には不向きな場合があります。ただし、長期的に認知を広げて見込み顧客を育てるという観点では有効であるため、目的に応じた戦略設計が求められます。
効果検証が容易ではない
ディスプレイ広告の効果測定は、クリック数やインプレッション数といった数値は把握しやすい一方、売上や問い合わせといった最終的な成果にどう影響を与えたかを正確に把握するのは容易ではありません。
特に、広告を見たがクリックせずに後日別の経路から購入したケースや、複数の広告がコンバージョンに寄与しているケースでは評価が複雑になります。さらに、広告フォーマットの種類や配信チャネルによって指標の意味合いも異なるため、単純に比較できません。
そのため、分析の際はアトリビューション分析などの手法を活用する必要があり、専門知識やリソースが不足している企業にとっては難易度の高い課題といえます。
広告費の消化が比較的早い
ディスプレイ広告は大規模に配信される傾向が強く、ターゲティングを広げれば一日に数千~数万のインプレッションを獲得できることもあります。しかし、この性質から広告費の消化が早くなりやすく、十分な効果が出る前に予算が尽きてしまうリスクがあります。
特に1クリック当たりの単価(CPC)が低めであるため出稿量を増やしやすい一方で、細かな調整を怠ると費用対効果が下がる可能性が高まります。そのため、効果を最大化するには配信面やターゲティング条件をこまめに見直し、無駄な表示や不要なクリックを抑えるためのチューニングが欠かせません。計画性と継続的な改善が重要です。
配信面ごとにクリエイティブ制作が必要になる
ディスプレイ広告は配信先となる媒体やフォーマットごとに表示形式やサイズが異なり、それに応じたクリエイティブを用意する必要があります。例えば、バナー広告では横長や正方形など複数のサイズを作成する必要があり、動画広告では秒数ごとに別パターンを用意する場合もあります。
さらに、媒体のユーザー層に合わせてトーンやデザインを調整する必要があり、クリエイティブ制作にかかる工数やコストが膨らみやすい点が課題となります。
制作リソースに余裕がない企業では更新頻度が下がり、広告効果が伸び悩むおそれがあります。そのため、事前に優先度を決め、効率的な制作プロセスを構築することが求められます。
ブランド毀損につながる可能性がある
ディスプレイ広告は多種多様なサイトやアプリに掲載されるため、意図しない不適切なコンテンツと一緒に表示されてしまうリスクがあります。例えば、過激な表現を含むサイトや、不正確な情報を含むページに広告が表示されると、ユーザーにマイナスの印象を与え、結果的に企業やブランドイメージを損ねる可能性があります。
さらに、広告の内容やデザインそのものがユーザーに不快感を与えるケースもあり、誤ったターゲティングや過剰な追跡(リマーケティング広告の過度な頻出など)が逆効果になることも少なくありません。そのため、ブランドセーフティの観点から配信面を厳しく制御し、自社に適した露出先を選定することが必須となります。
ディスプレイ広告フォーマット別のメリット・デメリット
この章では、ディスプレイ広告の主要なフォーマットごとの特徴やメリット・デメリットを解説します。
バナー広告
バナー広告は、ディスプレイ広告の中でも代表的な形式であり、Webサイトやアプリ内の指定枠に静止画やアニメーションを表示する方法です。
バナー広告のメリット
バナー広告はシンプルなデザインで出稿が容易で、多くの広告枠に対応できるため、Webやアプリ上で短期間に広いリーチを確保しやすいフォーマットになります。認知向上や初期接触のきっかけ作りに適しており、CTRが低めでもインプレッションを安定的に積み上げることで、潜在層への継続的な接触とブランド想起の拡大に寄与します。
バナー広告のデメリット
一方で、視認性が必ずしも高いとはいえず、広告への「慣れ」によりクリック率が低下しやすい傾向があります。出稿のハードルが低いため競合も多く、差別化にはクリエイティブの工夫が不可欠です。フォーマットの特性上、直接的なコンバージョン貢献は限定的になりやすく、短期の獲得指標とは相性が悪い場合があります。
動画広告
動画広告は、音声と映像を組み合わせて情報を伝える広告フォーマットです。YouTubeや各種SNS、アプリ内の動画枠などで配信されます。
動画広告のメリット
動画広告は、音声と映像を組み合わせて短時間で直感的に多くの情報を届けられるため、ストーリーテリングによるブランド訴求に適しています。動画配信プラットフォームやSNSとの親和性が高く、若年層を含む幅広いユーザーへの到達に有効です。また、冒頭で注意を引く設計や明確なメッセージ設計により、静止画よりも注意を喚起しやすい傾向があります。
動画広告のデメリット
一方で、制作コストや準備工数が静止画より大きくなりやすい点は注意が必要です。さらに、動画の長さや構成によって視聴完了率が大きく左右され、短尺設計・冒頭での訴求・モバイル前提の作り込みが求められます。
インストリーム広告
インストリーム広告は、主に動画配信サービスやYouTubeなどでコンテンツの前後、あるいは途中に再生される動画広告を指します。スキップ可能な形式やスキップ不可の形式など複数のタイプがあり、視聴体験の一部として自然に挿入される点が特徴です。
インストリーム広告のメリット
インストリーム広告は動画コンテンツと連続して表示されるため視認性が高く、ブランドや商品の世界観をストーリー仕立てで訴求できます。さらに、興味関心や行動履歴などのオーディエンスに基づく配信で、潜在層から顕在層まで幅広くアプローチ可能です。視聴を通じて一定時間接触することで記憶に残りやすく、認知や態度変容につながるフォーマットです。
インストリーム広告のデメリット
一方で、視聴体験を中断して配信されるため、不快感を与えるリスクがあり、スキップ率も高くなりがちです。動画制作にはコストや時間がかかり、品質が伴わないと効果が限定的になるおそれがあります。また、短期的なクリックや直接CVにはつながりにくい場合があり、中長期のブランド育成の観点で活用する設計が求められます。
カルーセル広告
カルーセル広告は、1つの広告枠内に複数の画像や動画をスライド形式で表示できるフォーマットです。ユーザーが横にスクロールして閲覧できる仕様で、ECサイトの商品紹介や複数のサービスラインナップの訴求に適しています。FacebookやInstagram、LinkedInなどのSNS広告で広く利用されている形式です。
カルーセル広告のメリット
カルーセル広告は複数のビジュアルを組み合わせて訴求できるため、商品やサービスの特徴を段階的に伝えられる点が強みです。単一の広告では伝えきれない多面的な魅力を表現でき、ストーリーテリングにも活用可能です。ユーザーにスクロール操作を促すことで、エンゲージメントが高まりやすく、CTRの改善や商品詳細ページへの誘導強化につながります。また、1つの広告枠で複数の商品を紹介できるため、EC事業者にとっては効率的なプロモーション手段になります。
カルーセル広告のデメリット
訴求内容を盛り込みすぎると煩雑になり、最初の数枚で関心を引けない場合は最後まで見られにくいリスクがあります。加えて、複数カード分のクリエイティブ制作が必要となり、運用の工数・コストが増えやすい点も課題です。短期の直接コンバージョンよりは、比較検討や理解促進の中間目的に適した場面が多いフォーマットです。
ネイティブ広告
ネイティブ広告とは、媒体のコンテンツやデザインと調和する形で表示される広告フォーマットです。記事やフィード、レコメンド枠などに自然に組み込まれ、ユーザーに違和感を与えにくい点が特徴です。ニュースサイトやSNS、キュレーションメディアなど、幅広い場面で利用されています。
ネイティブ広告のメリット
ネイティブ広告は、媒体のコンテンツに溶け込む形で表示されるため、広告感を抑えつつ情報を伝えられます。ユーザーの閲覧体験を妨げにくく、記事や投稿と同じ流れで接触できることで、エンゲージメントやブランド理解を自然に高めやすい点が強みです。特に記事型広告では、商品の利用シーンやストーリーを詳細に紹介できるため、比較検討段階のユーザーに有効です。また、配信先の媒体が持つ信頼感や権威性を借りられることも、ブランド価値の向上につながります。
ネイティブ広告のデメリット
一方で、広告とコンテンツの境目が分かりにくいため、ユーザーに誤解を与えるリスクがあり、媒体や広告主には、「広告である」ことを明示する責任があります。さらに、広告効果が短期的なクリックや即時購買につながりにくく、記事やコンテンツを読んでもらうまでに時間を要する傾向があります。制作には記事ライティングや取材などの工数がかかるため、一定のリソースやノウハウが必要となる点も課題です。
リッチメディア広告
リッチメディア広告は、動画やアニメーション、インタラクティブな要素を組み込んだ広告フォーマットで、ユーザーが操作や視聴を通じて体験できる点が特徴です。バナーやインストリーム広告に比べて表現力が高く、Webサイトやアプリ上で多様な形態で展開できます。
リッチメディア広告のメリット
リッチメディア広告は、視覚や聴覚に加えユーザーの操作も伴うため、没入感のある体験を提供できます。動画やアニメーションを活用することでブランドや商品の魅力を印象的に伝えられ、従来の静止画バナーより高いエンゲージメントが期待できます。さらに、クリックやタップ以外にも「スクロール量」「動画再生率」など多様な指標で効果を測定できるため、ユーザー行動をより深く分析できる点も強みです。特に新商品やキャンペーン告知においては、インパクトのある演出で、認知拡大に寄与します。
リッチメディア広告のデメリット
一方で、制作に高度なデザインや開発スキルが必要となり、コストや準備期間が大きくなりやすい点が課題です。また、ファイル容量が大きくなることで読み込み速度に影響を与え、ユーザー体験を損なうリスクもあります。さらに、派手な演出や強制的な操作がユーザーに不快感を与える場合もあり、適切なバランスが求められます。短期的なコンバージョンよりも、ブランド体験や印象形成を目的とした活用に適したフォーマットといえます。
動的ディスプレイ広告
動的ディスプレイ広告は、ユーザーの行動履歴や興味関心に基づいて、自動的に最適な商品やサービスを表示する広告フォーマットです。ECサイトや旅行サイトなどの商品ラインナップが豊富な業種で特に活用され、ユーザーごとに内容が変わる点が特徴です。
動的ディスプレイ広告のメリット
動的ディスプレイ広告は、ユーザーが閲覧した商品や関連性の高いアイテムを自動的に表示できるため、購買意欲が高まっているタイミングで再アプローチできます。従来のバナー広告に比べてパーソナライズ度が高く、クリック率やコンバージョン率の向上につながりやすいフォーマットです。特にカートに商品を入れたまま離脱したユーザーなどに対して効果的で、売上回収の強力な手段となります。また、クリエイティブは商品フィードと連携して自動生成されるため、大量の商品を扱う場合でも効率的に運用可能です。
動的ディスプレイ広告のデメリット
一方で、商品フィードの整備やタグの実装など、導入時に技術的な準備が必要となり、運用のハードルが高い点が課題です。また、ユーザーによっては「追いかけられている」と感じ、不快感を与えるケースもあり、配信頻度や期間の適切な調整が欠かせません。さらに、表示される商品はユーザーの過去の行動に依存するため、新商品の認知拡大や潜在層へのアプローチには適していない場合があります。
Related Articles