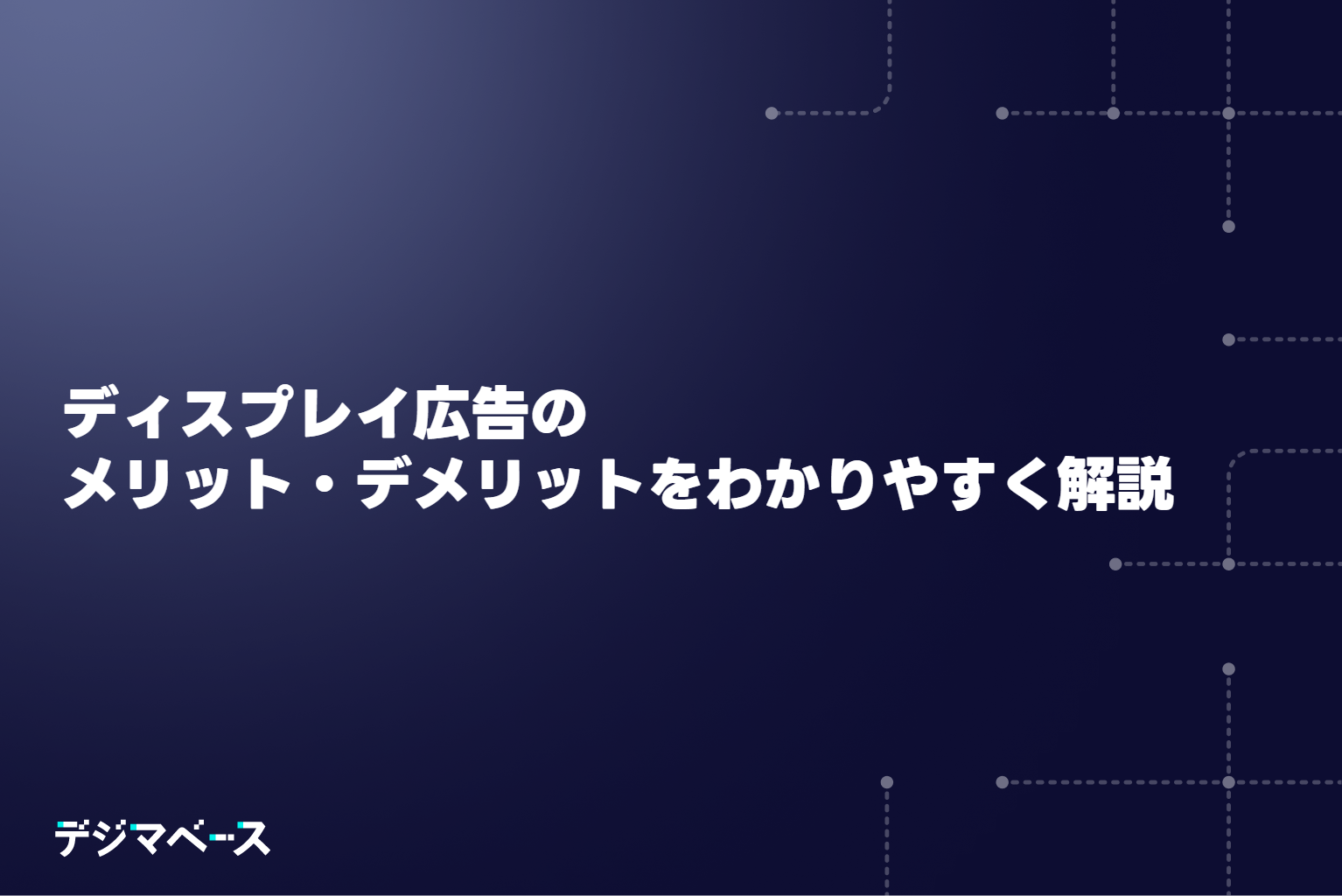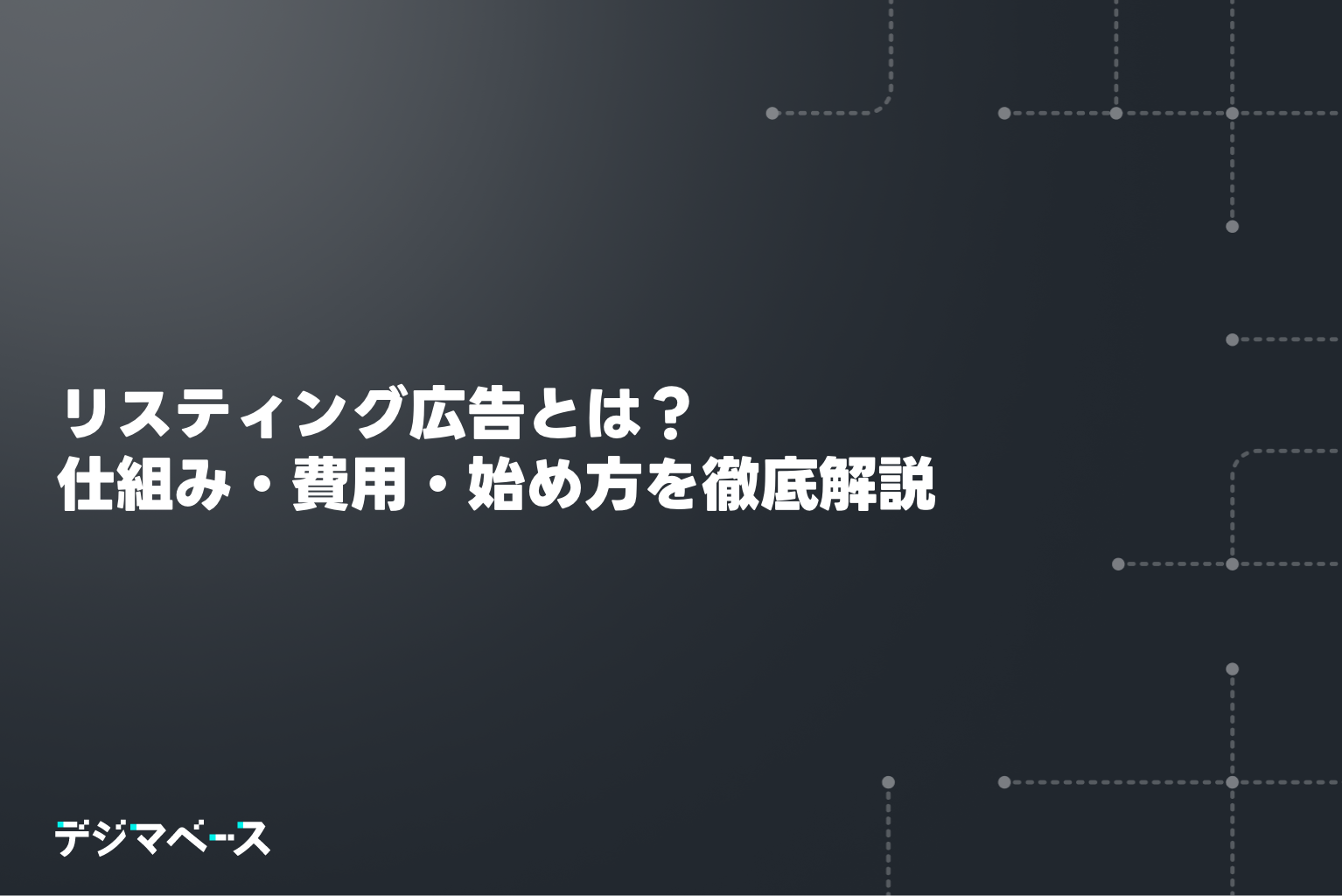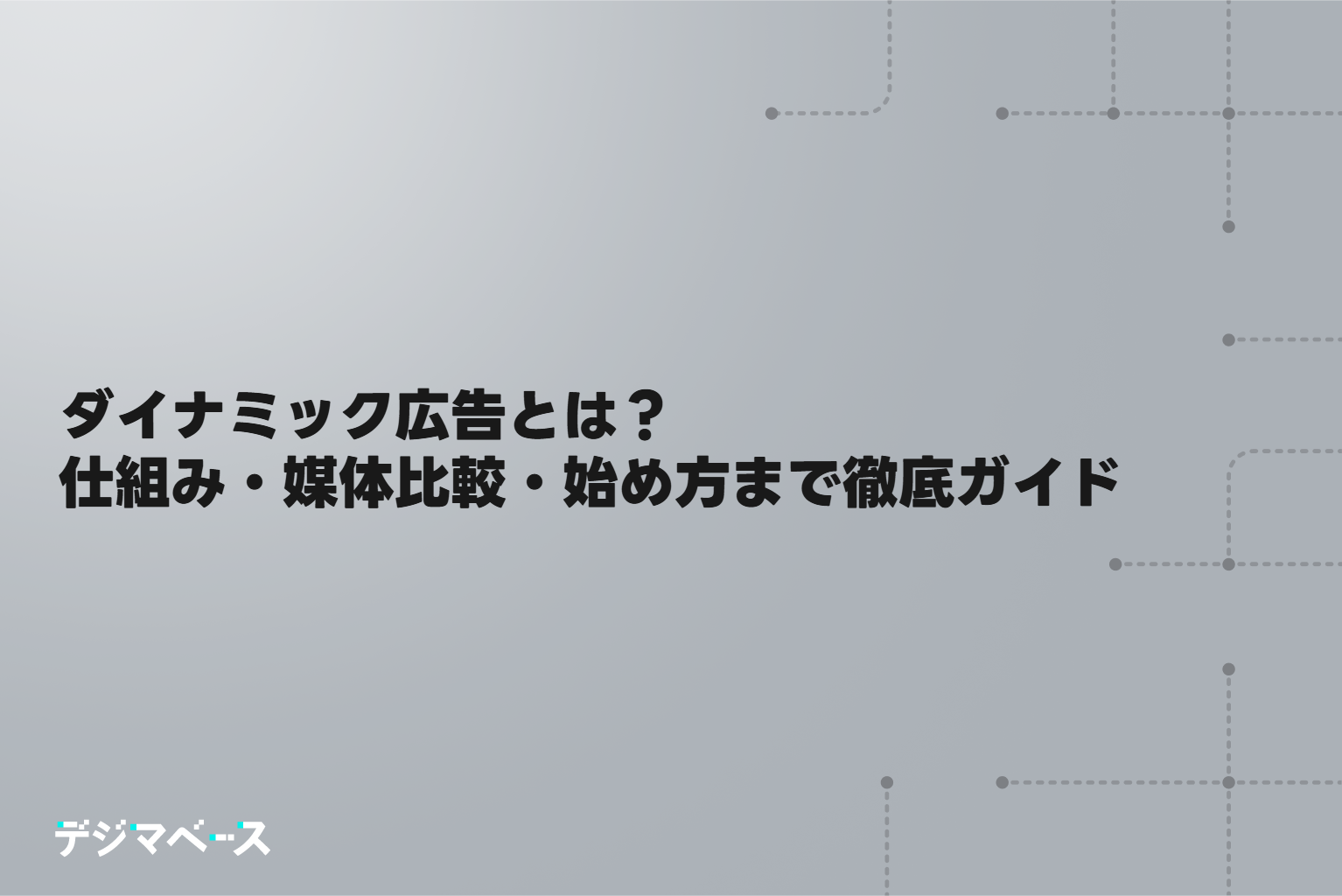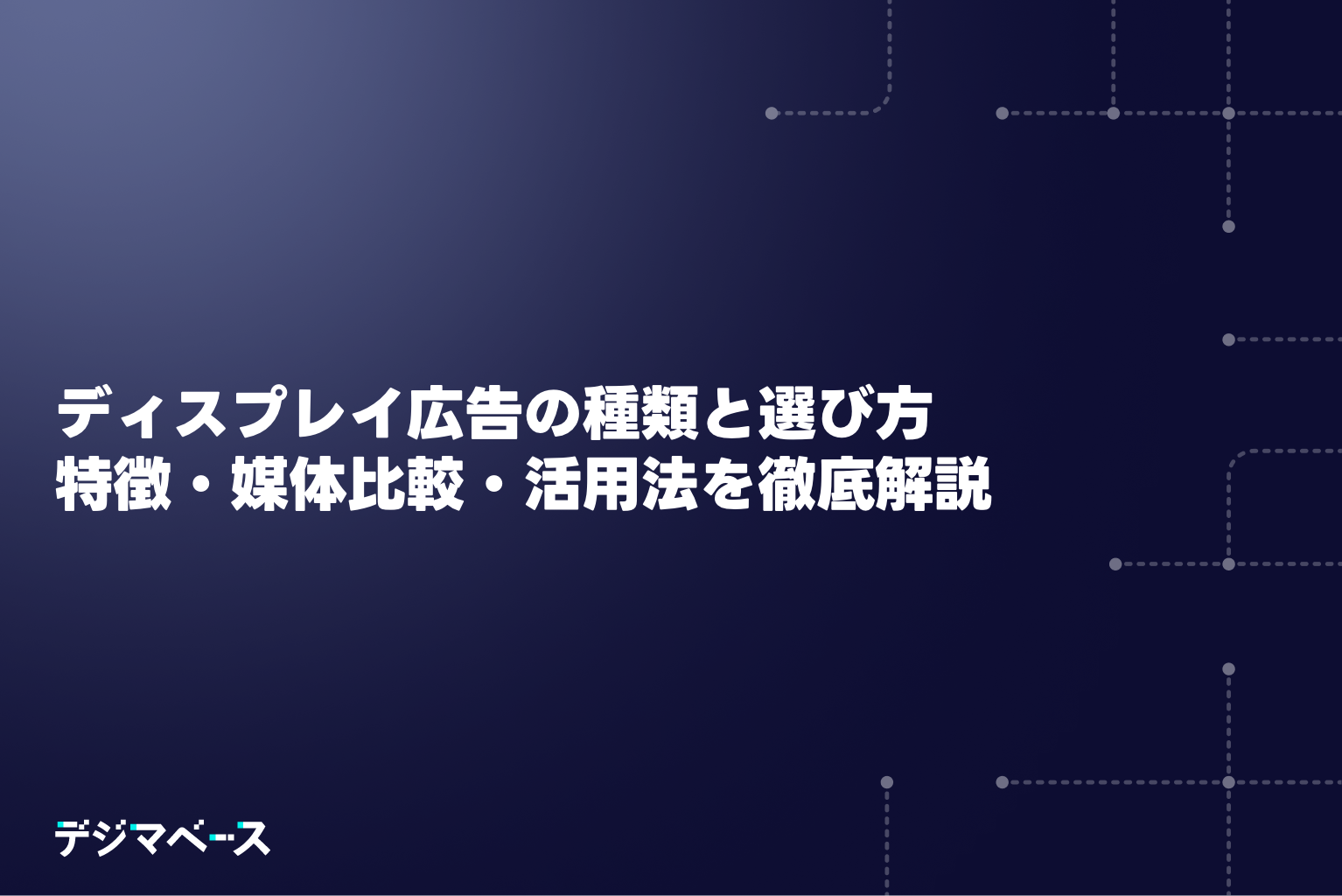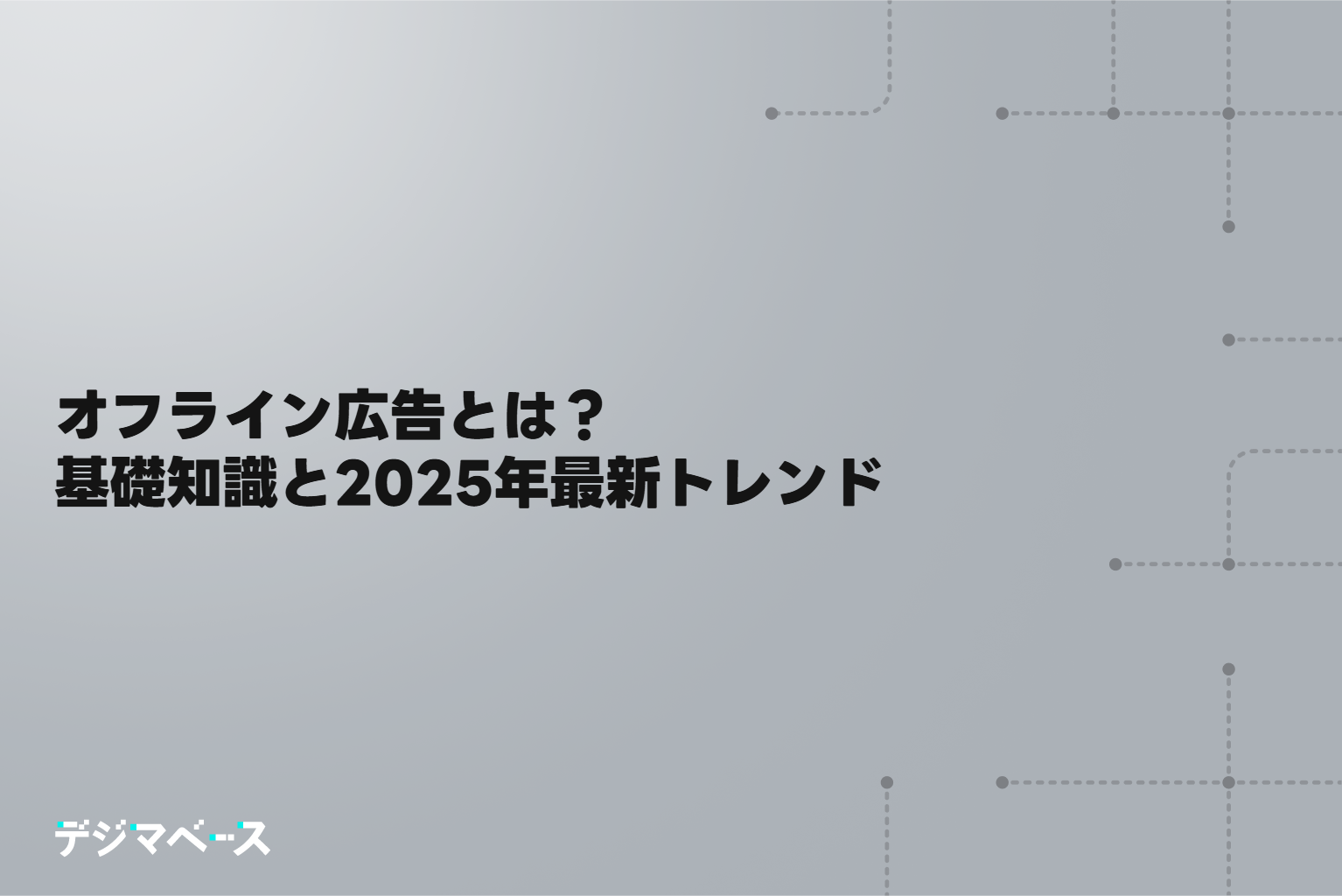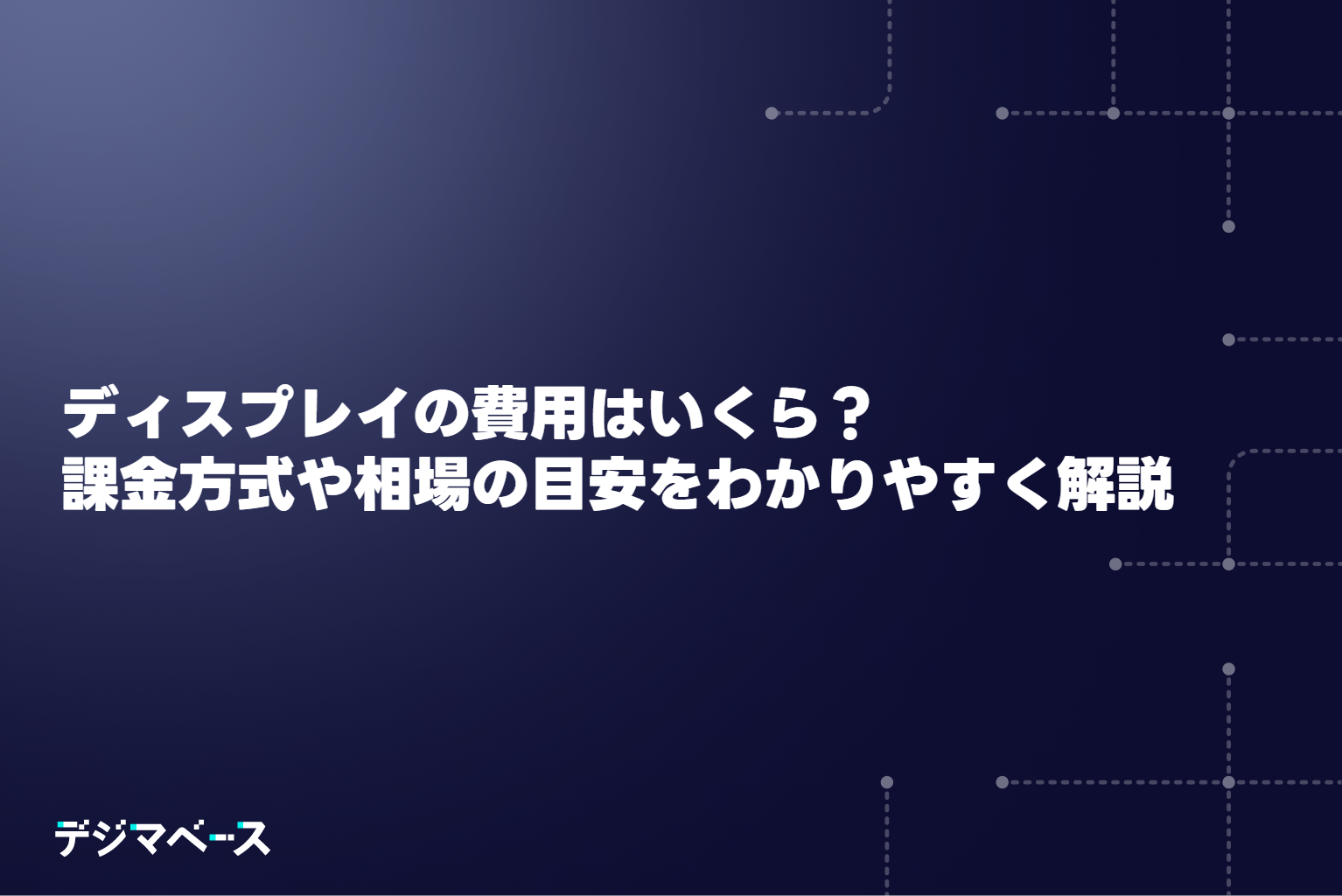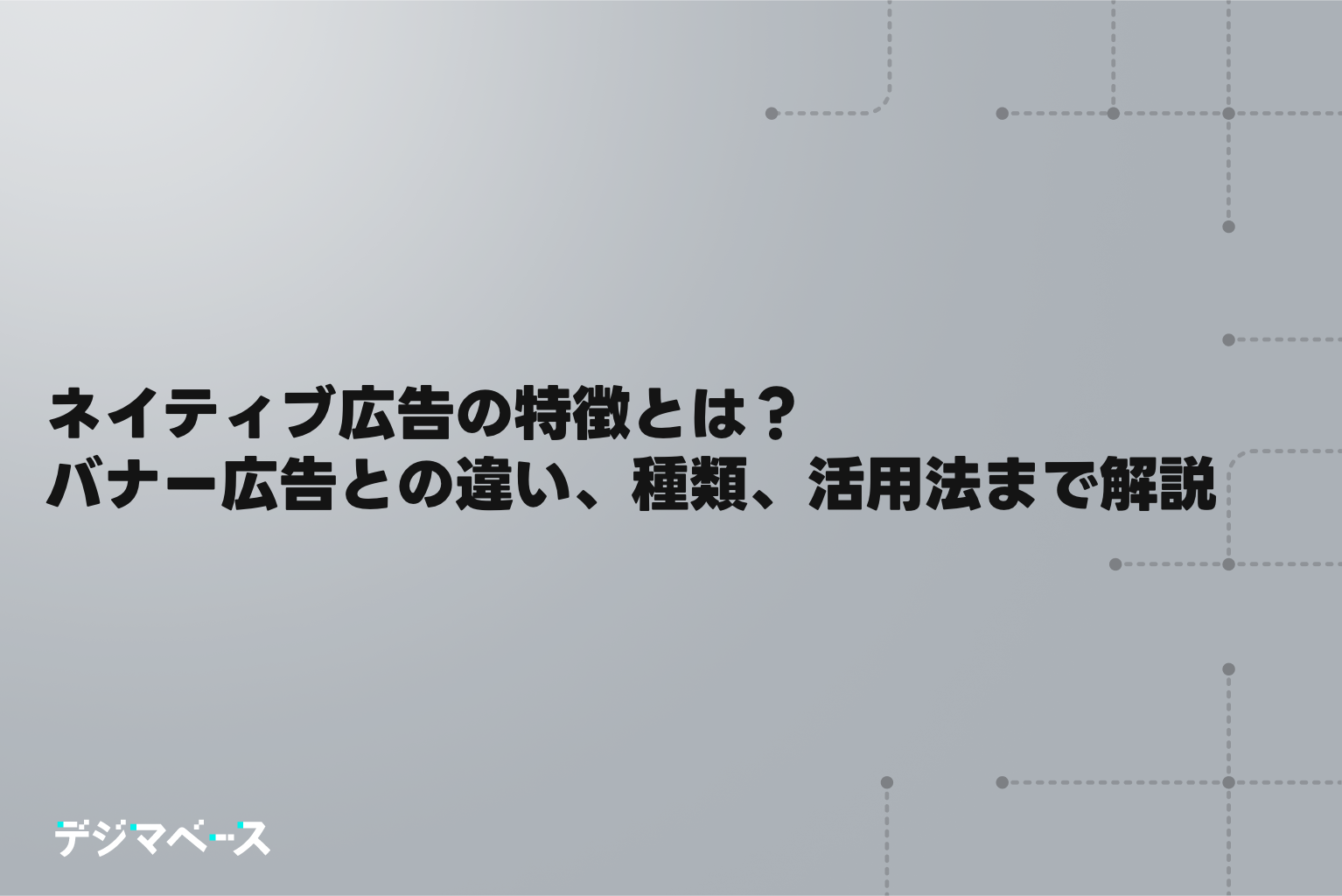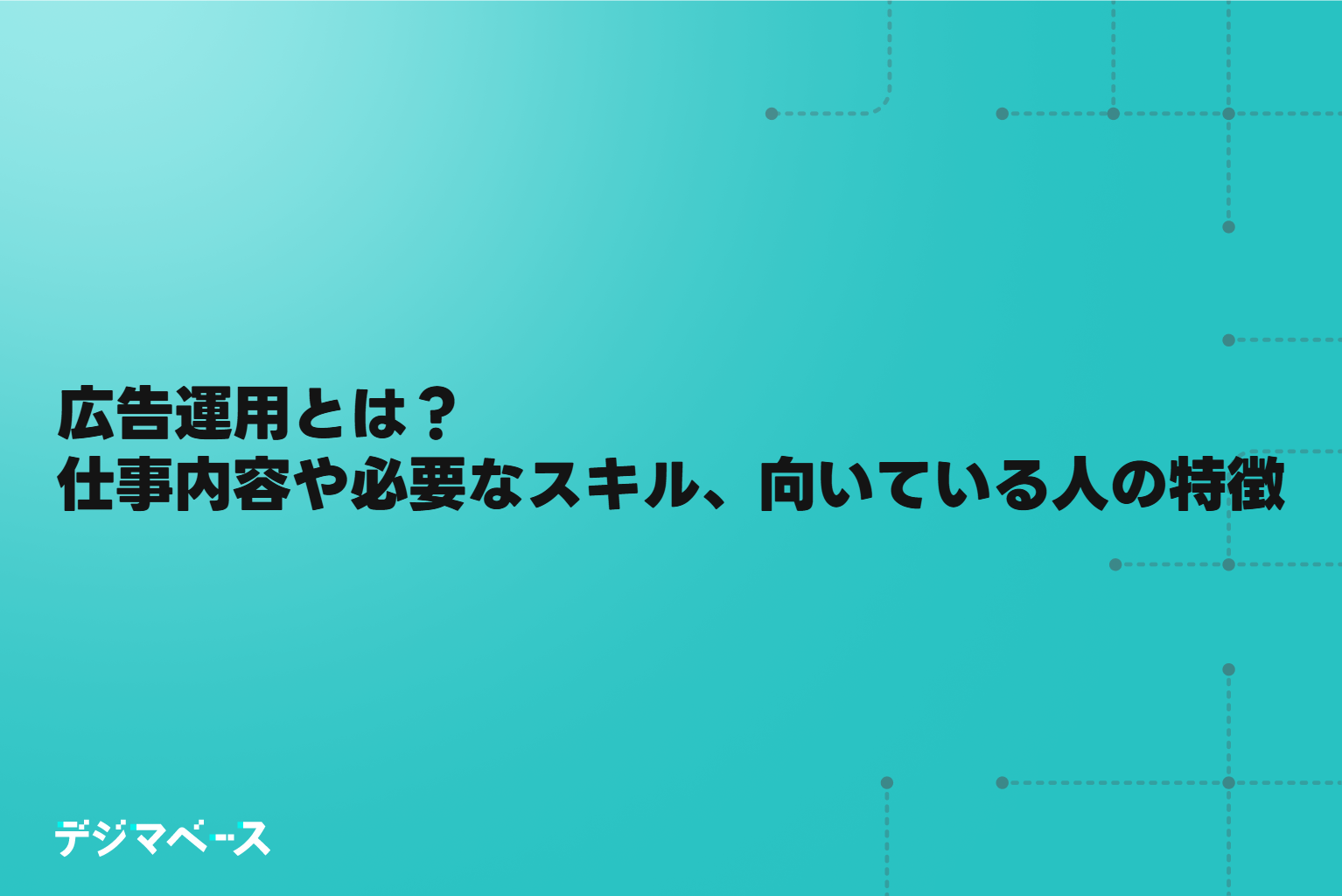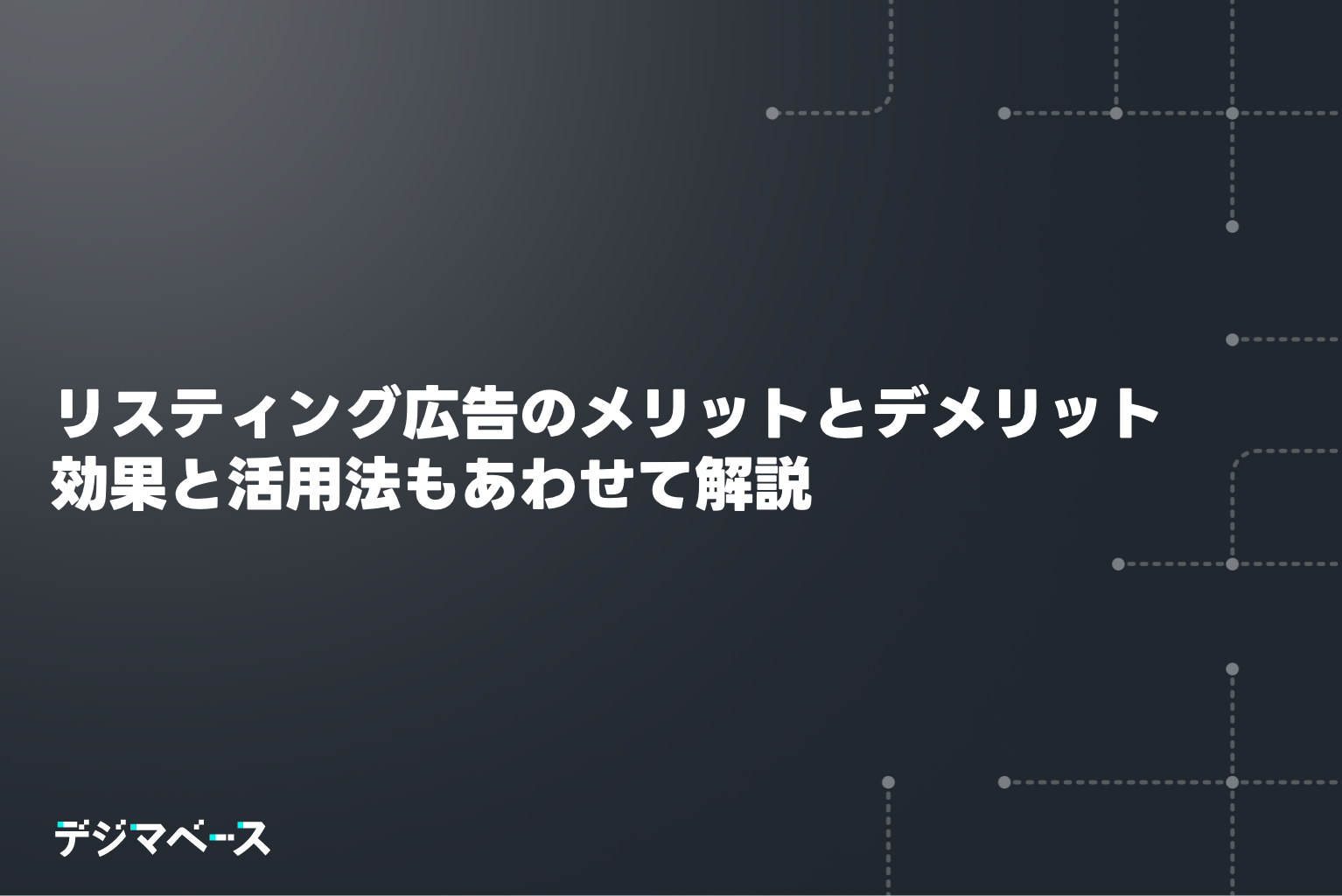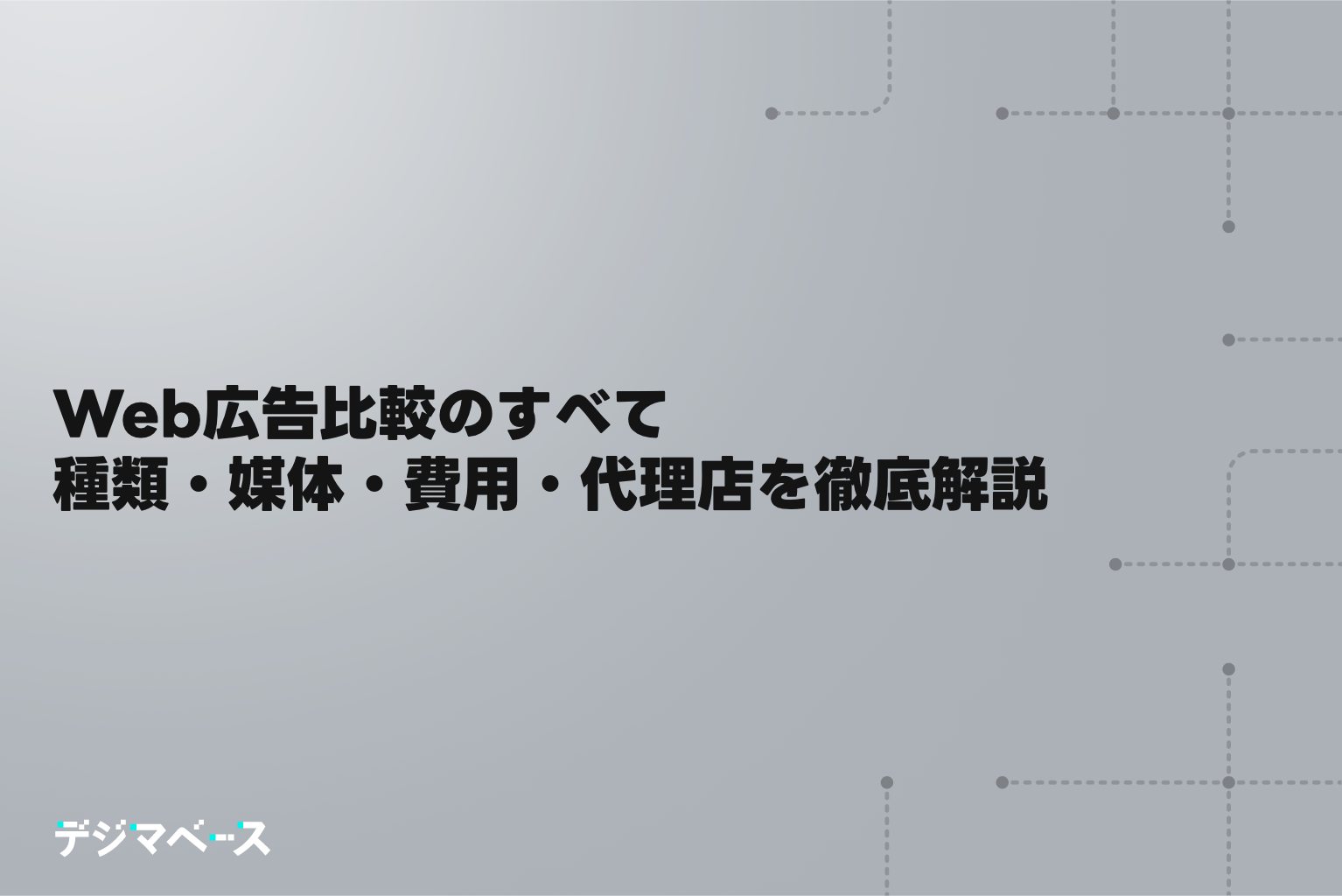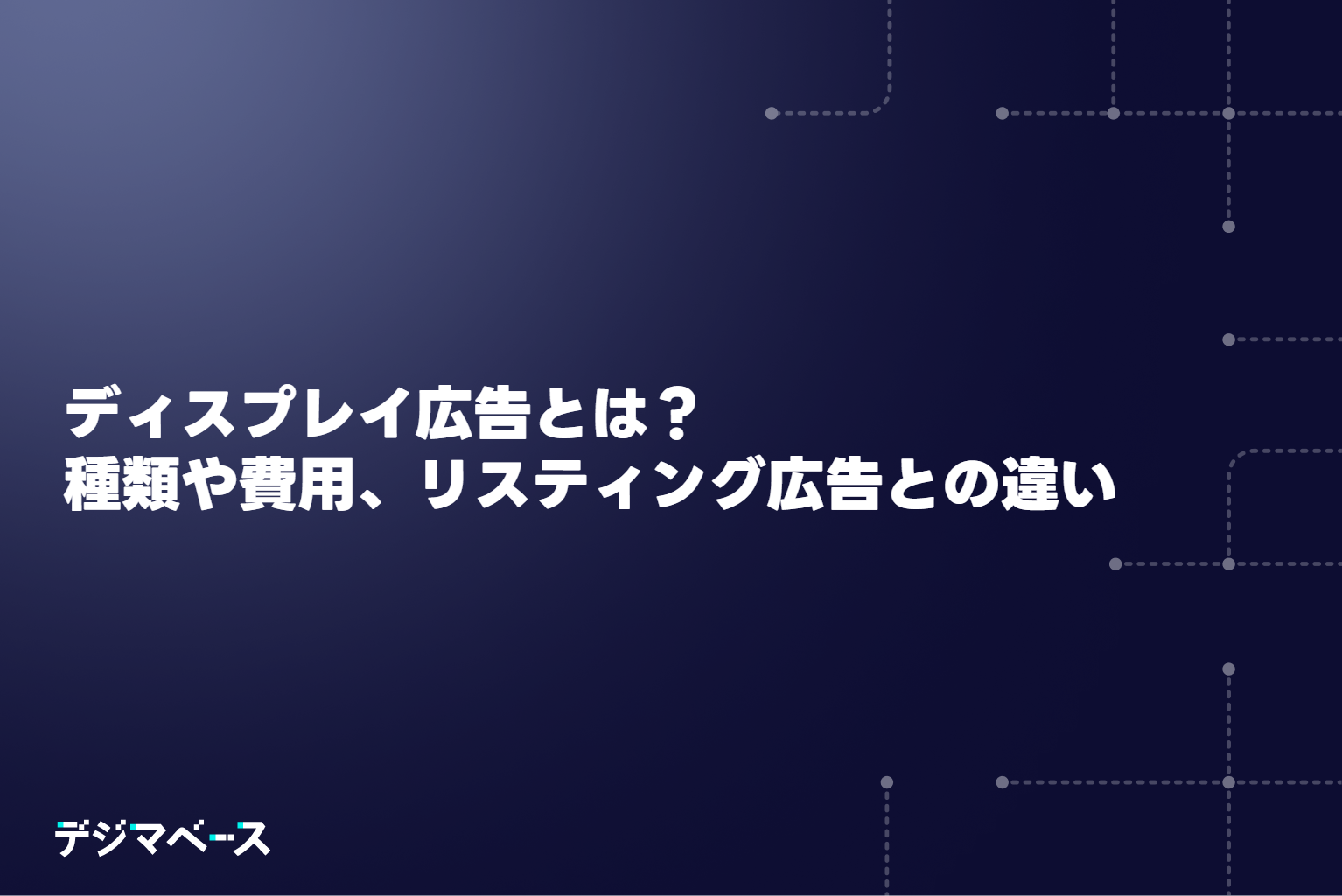
ディスプレイ広告とは? 種類や費用、リスティング広告との違いを解説
ディスプレイ広告とは、画像や動画で視覚的に訴求できるマーケティング手法です。本記事ではリスティング広告との違いや種類、費用、メリット・デメリットを解説し、成果を高めるためのコツも紹介します。
- 目次
ディスプレイ広告とは?
ディスプレイ広告とは、Webサイトやアプリの広告枠に表示される、画像や動画、テキストなどを用いた広告です。バナー形式で表示されることが多いため、「バナー広告」とも呼ばれます。ビジュアルで訴求できる点が特徴で、認知拡大や潜在層へのアプローチに適しています。
ディスプレイ広告は、特定のサイトの枠を買う「予約型広告(純広告)」と、広告枠や入札額などを調整して、成果を最大化する「運用型広告」の大きく2種類に分かれます。一般的に「ディスプレイ広告」は運用型を指すことが多いです。
さらに、ディスプレイ広告には「リターゲティング」という仕組みがあり、一度サイトを訪れたものの購入や問い合わせに至らなかったユーザーを再び広告で呼び戻すこともできます。これにより、見込み顧客を段階的にコンバージョンへ導く施策として活用される例もあります。
【関連記事】Web広告とは?初心者でもわかる仕組み・種類・メリットをやさしく解説
ディスプレイ広告とリスティング広告の違い
本章では、ディスプレイ広告とリスティング広告の違いについて、まずはリスティング広告の概要を説明した上で、違いを掘り下げていきます。
リスティング広告とは?
リスティング広告とは、「検索連動型広告」とも呼ばれ、ユーザーが検索エンジンで検索した際、そのキーワードや意図に応じて、テキスト形式の広告を表示する広告です。そのため、リスティング広告は顕在層へのアプローチに強みがあり、具体的な資料請求や問い合わせといった行動を促すことに向いています。
【関連記事】リスティング広告とは?仕組み・費用・始め方を徹底解説
具体的にリスティング広告と異なる部分
こちらでは、ディスプレイ広告とリスティング広告の違いを次の5つのポイントから解説します。
- 目的
- 広告の掲載場所
- 広告のフォーマット
- アプローチできるユーザー層
- クリック単価
目的
ディスプレイ広告とリスティング広告では、まず広告配信の主な目的や果たす役割が異なります。
ディスプレイ広告は、主に認知拡大や潜在層へのアプローチを目的としています。まだ商品やサービスに対して明確なニーズを持っていないユーザーにビジュアルや動画などの魅力的な表現でメッセージを届けることで、興味や関心を喚起します。
一方、リスティング広告は、ユーザーが検索エンジンでキーワードを入力した際、その検索意図に沿った広告を表示する仕組みです。そのため、リスティング広告は「顕在層」へのアプローチに強みがあり、購買検討や資料請求といった直接的な行動を促すのに適しています。
広告の掲載場所
広告がどこに表示されるかについても両者で異なります。
ディスプレイ広告は、Webサイト、アプリ、動画プラットフォーム、SNSなどの広告枠に掲載されます。例えばニュースサイト、ブログ、動画サービスなど生活の中で自然に目に入る場所に表示されるのが特徴です。そのため、ユーザーが特定の情報を検索していなくても接触機会を作ることが可能です。
一方、リスティング広告はGoogleやYahoo!の検索結果ページに掲載されます。特定のキーワードを検索した直後に表示されるため、強いニーズを示すユーザーにアプローチできるのが特徴です。
広告のフォーマット
広告のフォーマットにおいては、ディスプレイ広告は視覚的に訴求できる多様な形式に対応しています。具体的にはバナーや動画、アニメーションを用いたリッチメディア広告、ネイティブ広告など、多様な形式で商品やサービスの魅力を伝えられます。
一方、リスティング広告のフォーマットは基本的にテキスト広告です。検索意図に一致し、ユーザーのアクションを喚起するシンプルかつ魅力的な表現が求められます。
アプローチできるユーザー層
ディスプレイ広告は、潜在層に幅広くリーチできる特徴があります。特定のWebサイトに訪問した経験や属性情報、興味・関心データをもとにターゲティングすることで、まだ商品を購入しようと考えていないユーザーに情報を届けやすいのが強みです。また、過去に自社サイトに訪問したユーザーへ改めて広告を配信するリターゲティング、購入を迷っているユーザーに再度訴求することが可能です。
対して、リスティング広告は検索キーワードに基づく配信であるため、購買意欲がすでに高い「顕在層」へのアプローチが中心です。例えば「東京 ホテル 予約」など検索クエリ(キーワード)が具体的なニーズを示す場合、コンバージョンしやすいユーザーが集まる傾向があります。
このように、ディスプレイ広告は幅広い層を巻き込み認知を高めるのに適し、リスティング広告は購入や申し込みに近い行動を狙う際に適していると言えます。
クリック単価
広告費の面では、ディスプレイ広告の方が比較的クリック単価が安価になる傾向があります。これは幅広いユーザーへの認知を目的とし、必ずしも即時的な成果を狙わないため、低コストで大量の接触が見込めるためです。
一方で、リスティング広告のクリック単価は、人気の高いキーワードや競合の多い業種では、1クリックで1,000円以上になる場合も少なくありません。これは購買意欲の高い顕在層に直接リーチできることから、競争が激しくなるためです。
ディスプレイ広告の種類
本章では、ディスプレイ広告の媒体と表示形式(フォーマット)の2つの観点から、それぞれどんなものがあるのかを解説します。媒体やフォーマットの特徴を知ることで、最適なメディアプランニングにつながります。
媒体
こちらでは次の主要なディスプレイ広告媒体について説明します。
- Google ディスプレイ ネットワーク(GDN)
- YouTube広告
- Yahoo!広告 ディスプレイ広告(運用型)
- LINE広告
- Meta広告(Facebook / Instagram)
- TikTok広告
Googleディスプレイネットワーク(GDN)
Google ディスプレイ ネットワーク(GDN)は、GmailやYouTube、提携サイトに広告を配信できるネットワークです。世界中の媒体が対象となるため、圧倒的な配信規模を誇ります。GDNを利用することで、世界中のインターネットユーザーの90%超に広告を表示することが可能です。
YouTube広告
YouTube広告は、世界最大級の動画プラットフォームであるYouTube上に表示される広告です。動画再生前後や動画再生中に表示される広告や、検索画面や関連動画一覧に表示されるものなどがあります。幅広い年齢層が利用しており、ブランド認知や商品理解を深めるのに適しています。また、Googleアカウントと連携したターゲティングも可能です。
Yahoo!広告 ディスプレイ広告(運用型)
Yahoo!広告 ディスプレイ広告(運用型)は、Yahoo!ニュースや天気といった国内で多くのユーザーが利用するサービスに加えて、提携するさまざまなWebサイトやアプリに広告を配信できるディスプレイ広告です。多くの人が利用するYahoo! JAPANのさまざまな掲載面に出稿できるため、日本全国の幅広いユーザーに広告を届けられます。
LINE広告
LINE広告は、幅広い世代のユーザーが日常的に利用するLINEや関連サービスに広告を配信できるサービスです。月間アクティブユーザーが9,900万人を超えるサービスにおいて、他媒体ではリーチできないユーザーにアプローチできる点が特徴です。また、LINE公式アカウントと組み合わせることで見込み顧客とのコミュニケーションを継続できる点も強みと言えます。
Meta広告(Facebook / Instagram)
Meta広告(Facebook / Instagram)は、Meta社が運営するSNS媒体への配信が可能で、ターゲティング精度に定評があります。ユーザーの属性(年齢、性別、地域など)だけでなく、趣味や行動履歴に基づいた配信が可能です。Instagramは視覚的な投稿が中心で、ブランドイメージ訴求やEC商品の販売促進に適しています。一方でFacebookは幅広い世代に利用されており、BtoB用途でも活用できます。
X(旧Twitter)広告
X(旧Twitter)の広告は、拡散力の高さが特徴です。ユーザーが気軽にリポスト(旧リツイート)や共有を行うため、広告が自然に拡散され、短期間で話題性を獲得できる点が強みとなります。そのため、リアルタイム性の強いプロモーション、例えばキャンペーンやイベント告知に適しています。加えて、広告フォーマットもテキストや画像、動画、カルーセル(複数の画像や動画をスライドして閲覧できる広告)など多彩で、目的に応じた柔軟な運用が可能です。
TikTok広告
TikTok広告は短尺動画を主体とする比較的新しい媒体で、特に若年層へのリーチに優れています。ユーザーが数秒から数十秒の動画を次々に閲覧するスタイルのため、インパクト重視のクリエイティブが効果的です。トレンドを意識した広告運用を行えば高いエンゲージメントを獲得が期待できます。加えて、アプリダウンロードやEC商品購入へのスムーズな導線設計が可能で、近年急速にマーケティングで活用が進んでいます。
表示形式(フォーマット)
ディスプレイ広告は媒体による違いだけでなく、広告の表示形式も多様です。形式の選択次第でユーザーへの伝わり方や効果が大きく変わるため、目的に応じた最適なフォーマットの利用が重要です。ここでは代表的な4種類を紹介します。
- バナー広告
- 動画広告
- ネイティブ広告
- リッチメディア広告
バナー広告
バナー広告は、Webページやアプリ上に表示される画像形式の広告です。一般的に正方形や長方形の枠を用い、画像やテキストを組み合わせて表示します。簡易的に認知を獲得できる一方、単純な表示だけではクリック率は高くないため、強い訴求ポイントを持たせることが大切です。表示面が広がればブランドのイメージを繰り返し届けられ、ブランディング施策に向いています。
動画広告
動画広告は、映像と音声を用いて商品やサービスを訴求する形式です。YouTubeやTikTokなど動画を中心としたプラットフォームだけでなく、SNSやWebサイトにも配信可能です。映像情報はテキストや画像よりも短時間で内容を伝えやすく、ユーザーの感情に訴えやすいメリットがあります。ただし、制作コストが比較的高くなりやすいため、十分に計画した上で作成することが重要です。
ネイティブ広告
ネイティブ広告は、コンテンツやUIのデザインに溶け込む形で表示される広告を指します。ユーザーが自然な記事や投稿の一部として閲覧できるため、広告感が薄く、受け入れられやすい特徴があります。SNSフィード内やニュースアプリの記事一覧になじむ形で配信されることが多く、配信内容と関連性の高い情報を組み合わせることで高い効果が期待できます。
リッチメディア広告
リッチメディア広告は、アニメーションやインタラクティブな要素を含む高機能な広告フォーマットです。ユーザーが操作したりアニメーションを体験したりできるため、強い印象を残すことが可能です。
- スワイプやタップで操作できる広告
- アニメーションや動画を組み合わせた動的表現
- 商品カタログを閲覧できるインタラクティブ表示
- 広告内で簡易なゲームがプレイできる体験
こうした表現を生かして、EC商品紹介やブランド体験を訴求するのに効果的です。加えて、ゲームアプリではプレイアブル広告を用いることで操作感やゲーム性を広告内で体験してもらえるため、インストール意欲の喚起にも適しています。一方で、実装や検証の負荷が高くなり、制作コストが上がる場合があります。
ディスプレイ広告の費用と課金方式
ディスプレイ広告の費用は、広告の目的とその課金方式によって異なります。こちらでは代表的な3つの課金方式について解説します。
- クリック課金
- インプレッション課金
- コンバージョン課金
クリック課金
クリック課金とは、ユーザーが広告をクリックした瞬間に広告主に費用が発生する課金方式です。一般的に「CPC(Cost Per Click)」と呼ばれ、ディスプレイ広告だけでなくリスティング広告でも採用されています。
広告が表示されるだけでは費用が発生しないため、実際にユーザーの興味を引いた分だけ支払いが発生するのがメリットです。目安は1クリックあたり数円〜数百円で、業界や競合度によって変動します。
インプレッション課金
インプレッション課金とは、広告がユーザーに表示された回数に応じて費用が発生する仕組みで、代表的なものに「CPM(Cost Per Mille)」があります。
これは1,000回の表示ごとに設定された料金が請求される形式のことで、認知拡大やブランドの周知を目的とした広告キャンペーンで用いられます。クリックに依存せず表示自体に価値を置くため、購入意欲がまだ高くない潜在層へのアプローチにも適しています。
費用は、1,000回の表示あたり数十円から数千円程度が目安ですが、業界や配信面、フォーマットで大幅に変動します。
コンバージョン課金
コンバージョン課金とは、ユーザーが広告を通じて問い合わせ、購入、資料請求といった具体的なコンバージョンをしたときにのみ費用が発生する方式です。「CPA(Cost Per Action)」とも呼ばれ、成果報酬型の課金形態となります。
広告費が実際の成果に直結するため、費用対効果が明確であり、無駄なコストを抑えやすいのが特徴です。ただし、広告媒体や業種によっては単価が高めに設定されることがあり、1コンバージョンあたり数千円から数万円となるケースもあります。
ディスプレイ広告のメリット
ディスプレイ広告には、潜在層へのアプローチ以外にもさまざまなメリットが存在します。どんなメリットがあるのかを理解した上で、広告を運用しましょう。
- 潜在層にアプローチできる
- ビジュアルで訴求できる
- リターゲティングできる
- クリック単価が比較的安価になる
- 認知獲得やブランディングができる
潜在層にアプローチできる
ディスプレイ広告のメリットの1つ目は、まだ商品やサービスに関心を示していない潜在層へリーチできることです。ニュースサイトやブログ、SNSを閲覧している段階で広告を表示することで、ユーザーが検索をする前に、商品やサービスを認知してもらえます。認知に限らず購入のきっかけを作りやすい点もメリットと言えるでしょう。
ビジュアルで訴求できる
2つ目のメリットは、テキストのみの広告とは異なり、画像や動画を使った視覚的な訴求ができる点です。商品画像や実際のサービス利用シーンをダイレクトに提示できるため、ユーザーに印象を残しやすく、購入意欲を喚起する効果も期待できます。
特にファッションや飲食、旅行など、ビジュアル要素が購入判断に影響しやすい業界では特に有効です。
リターゲティングできる
3つ目のメリットは、過去に自社のサイトやアプリを訪れたものの購入や申し込みに至らなかったユーザーに、再度広告を配信できるリターゲティングと呼ばれる仕組みがある点です。すでに興味を持っているユーザーに絞って購入意欲を高める広告を配信するため、効率的に成果を高められます。
クリック単価が比較的安価になる
4つ目のメリットは、リスティング広告に比べて、クリック単価、いわゆるCPC(Cost Per Click)が比較的安価になる傾向がある点です。
その理由は、広告の掲載枠が検索結果ページのように限定的でなく、インターネット上のさまざまなサイトやアプリに配信できるためです。結果として競合入札が集中しにくく、費用を押さえた広告出稿が可能です。
認知獲得やブランディングができる
5つ目のメリットは、ディスプレイ広告は直接的な購買や申し込みを促すだけでなく、認知獲得やブランディングにも効果的である点です。
例えば、ユーザーが日常的に利用するニュースサイトやSNS上で繰り返し広告を目にすることで、無意識のうちにブランド名やサービス名を記憶に刻むことができます。この接触の積み重ねが、後の検索行動や購入の意思決定に影響するのです。
ディスプレイ広告のデメリット
ディスプレイ広告には多くのメリットがある一方で、即効性に欠けることや効果測定が難しいといったデメリットも存在します。あらかじめリスクを知り備えておきましょう。主なデメリットは次のとおりです。
- 即時的な効果に結び付きづらいことがある
- 効果検証が容易ではない
- 広告費の消化が早い
- 配信面に合わせてクリエイティブの制作が必要になる
- ブランド毀損のおそれがあるサイトに配信される可能性がある
即時的な効果に結び付きづらいことがある
ディスプレイ広告は、潜在的なターゲット層に対してアプローチをかける性質が強い広告です。そのため、クリックや閲覧の段階で即座にコンバージョンへ結びつきづらく、成果の実感が出るまでに一定の時間がかかることがあります。
特に商品やサービスが比較検討されやすい高単価商材やBtoB領域では、ユーザーが広告を目にしてから購入や問い合わせに至るまでの期間が長くなりやすいため、短期的な効果を求める場合には不向きと言えるでしょう。
したがって、ディスプレイ広告を運用する際には「すぐに売上を生み出す」よりも「中長期的に認知や興味を積み重ねる」といった戦略意識が必要です。
効果検証が容易ではない
ディスプレイ広告の効果測定は、直接的な数値成果だけでなく、認知拡大やブランディングといった定性的な価値も考慮する必要があるため、検証が容易ではありません。例えば、コンバージョンに至るまでの複数の接点のうち、どの広告がどの程度貢献したのかを明確に切り分けるのは難しい場合があります。
また、表示回数やクリック数は計測できますが、それが本当にユーザーの購買意欲や態度変容に結びついたのかを判断することも効果検証が難しい理由の1つです。
加えて、配信媒体やターゲティングの種類によっても成果の指標が異なるため、適切なKPIを設計する必要が出てきます。特に初心者の運用担当者は「クリック数が多い広告=効果が高い」と早計に判断しがちなため、データの見方や評価軸を慎重に設計することが不可欠です。
広告費の消化が早い
ディスプレイ広告は表示される範囲が非常に広いため、短期間で大きなインプレッションを獲得できる一方、広告費が早く消化されやすいという特性があります。
特にインプレッション課金を採用している場合、クリックされなくても広告が表示されるだけで費用が発生するため、配信設定次第では短期間で予算を消費し、思った以上にコストが膨らむリスクがあります。
さらにターゲティングを十分に絞らないまま配信を開始すると、購入意欲の低いユーザーにまで広告が広がり、費用対効果が低下するおそれがあります。
そのため、ターゲット条件や配信デバイス、時間帯を適切に制限し、運用中も予算消化ペースを都度確認することが求められます。
配信面に合わせてクリエイティブの制作が必要になる
ディスプレイ広告では、Webサイト、アプリ、SNSなど多岐にわたる配信面が存在し、それぞれに求められる広告フォーマットやユーザーの閲覧行動が異なります。そのため、1種類のクリエイティブを使い回すだけでは効果を最大化できず、媒体やフォーマットに最適化した複数のバナーや動画などを用意する必要があります。
例えば、SNSでは短時間で印象を与える動画が有効ですが、ニュースサイトでは読みやすく違和感のないネイティブ広告が好まれる傾向があります。
また、広告面のサイズごとに最適化が必要で、制作リソースが大きくなりがちです。
こうした背景から、広告の質を維持しつつ効率的に制作体制を整えることが、ディスプレイ広告の運用における課題のひとつとなります。
ブランド毀損のおそれがあるサイトに配信される可能性がある
ディスプレイ広告はネットワークを通じて多様なサイトやアプリに配信されるため、運営側が意図しない掲載面に広告が表示されるリスクが存在します。特にアダルトや虚偽情報を扱うサイト、あるいは過激なコンテンツを含むページに表示されてしまうと、ユーザーに不快感を与えるだけでなく、企業ブランドの信頼を損なうおそれがあります。
大手の広告配信ネットワークにはこれを防ぐブランドセーフティ機能が備わっているものの、完全にリスクを排除することは困難です。そのため、配信先の除外設定やプレースメント指定を活用し、自社ブランドを守るための施策を講じる必要があります。
また、定期的に配信レポートを確認し、望ましくない媒体への露出を早期に把握・改善する体制が求められます。
【関連記事】ディスプレイ広告のメリット・デメリットをわかりやすく解説
ディスプレイ広告の成果を高めるためのコツ
この章では、ディスプレイ広告で成果を高めるためのコツを解説します。日々の業務のなかで忘れがちな基本をしっかりと押さえておきましょう。
- 広告の配信目的を明確にする
- 訴求軸に合わせてクリエイティブを制作する
- リターゲティングを活用する
- 広告とLPの内容を一致させる
- 効果の高い配信面に絞る
- 成果を計測しPDCAを回す
広告の配信目的を明確にする
ディスプレイ広告を成功させるためには、まず広告の配信目的を明確化することが重要です。
広告には「認知拡大」「商品・サービスの訴求」「コンバージョン獲得」など複数の役割がありますが、目的によって設定すべき指標や最適な入札方式が変わります。例えば、ブランディング目的であればインプレッション数を重視し、獲得目的であればコンバージョン単価やコンバージョン率を重視してKPIを設定する必要があります。
目的があいまいなまま配信を開始すると、成果指標が曖昧となり改善の方向性を見失いがちです。配信前に社内で共通認識を作り、KPIやKGIを明確に設定することが、効率的な広告運用の第一歩になります。
訴求軸に合わせてクリエイティブを制作する
ディスプレイ広告はビジュアル要素が大きく影響するため、配信目的やターゲットに沿った訴求軸を明確にしたクリエイティブ制作が求められます。例えば、認知向上が目的ならブランドカラーを活かした統一感のあるデザインにする。販売促進目的なら期間限定のキャンペーンコピーを大きく訴求するといった具合です。
静止画と動画で訴求力も異なるため、ターゲットがよく利用する媒体に応じて適切なフォーマットを選択することも必要になってきます。
さらに、複数パターンを作成してABテストを行うことで、より反応の高い訴求表現を発見できます。広告を目にした瞬間にユーザーが行動を起こしたくなるよう、明確で引きの強いメッセージ作りを心がけましょう。
リターゲティングを活用する
ディスプレイ広告で成果を効率的に高めるための代表的な施策がリターゲティング広告です。これは、一度サイトを訪れたユーザーや特定の行動を取ったユーザーに再度広告を配信する仕組みで、コンバージョンにつながる可能性が高いユーザー層にアプローチできます。
例えば、商品ページを閲覧したが購入に至らなかったユーザーに限定して広告を配信すれば、検討段階で離脱した見込み顧客を再び購買に導けます。
ただし、同じユーザーに過剰に配信すると広告疲れを引き起こすリスクもあるため、フリークエンシーキャップと呼ばれる1名のユーザーに広告を表示する回数上限を設けて接触回数を制御することが大切です。
広告とLPの内容を一致させる
ディスプレイ広告で成果を出すには、広告クリエイティブとリンク先のランディングページ(LP)の内容を一致させることが不可欠です。
広告で「初回限定50%オフ」と訴求しているのに、クリック後のLPにその情報がないと、ユーザーの信頼を損ねて離脱を招きます。逆に、広告とLPが一貫性を持つことで「自分が求めていた情報と一致している」と感じてもらえ、自然に行動につながりやすくなります。
また、LPのファーストビューに広告で訴求したコピーやビジュアルを反映すると、ユーザーは安心して先のコンテンツを読み進めます。広告とLPをセットで設計し、シームレスな体験を提供することがコンバージョン率向上の鍵です。
効果の高い配信面に絞る
ディスプレイ広告は数多くの配信面に表示可能ですが、成果を最大化するには効果の高い配信面に絞る取り組みが大切です。すべての配信先に一律で広告を打ってしまうと、広告費の浪費につながる可能性があります。
そのため、配信後のデータをもとに、クリック率やコンバージョン率の高いサイトやアプリに限定して配信するよう設定を最適化します。例えば、子育て世代をターゲットにした商材であれば、ニュースサイトよりも育児系のメディアやコミュニティサイトが成果を出しやすいことがあります。
成果を計測しPDCAを回す
ディスプレイ広告の運用は設定して終わりではなく、成果を継続的に計測し、PDCAサイクルを回すことが必須です。配信後にはクリック数やクリック率(CTR)、コンバージョン数などのKPIをチェックし、改善余地の大きい箇所を見極めます。
例えば、クリック率が高いのにコンバージョン率が低い場合は、LPの改善が必要と判断できますし、逆にCTRが低ければクリエイティブやターゲティングの見直しが必要となります。また、季節や時期によって成果が変動するケースもあるため、定期的にデータを比較・分析することが欠かせません。
改善策を小さく実行し、その効果を再度測定して修正していくことで、広告パフォーマンスは着実に向上していきます。データドリブンな運用姿勢が成功への近道です。
Related Articles