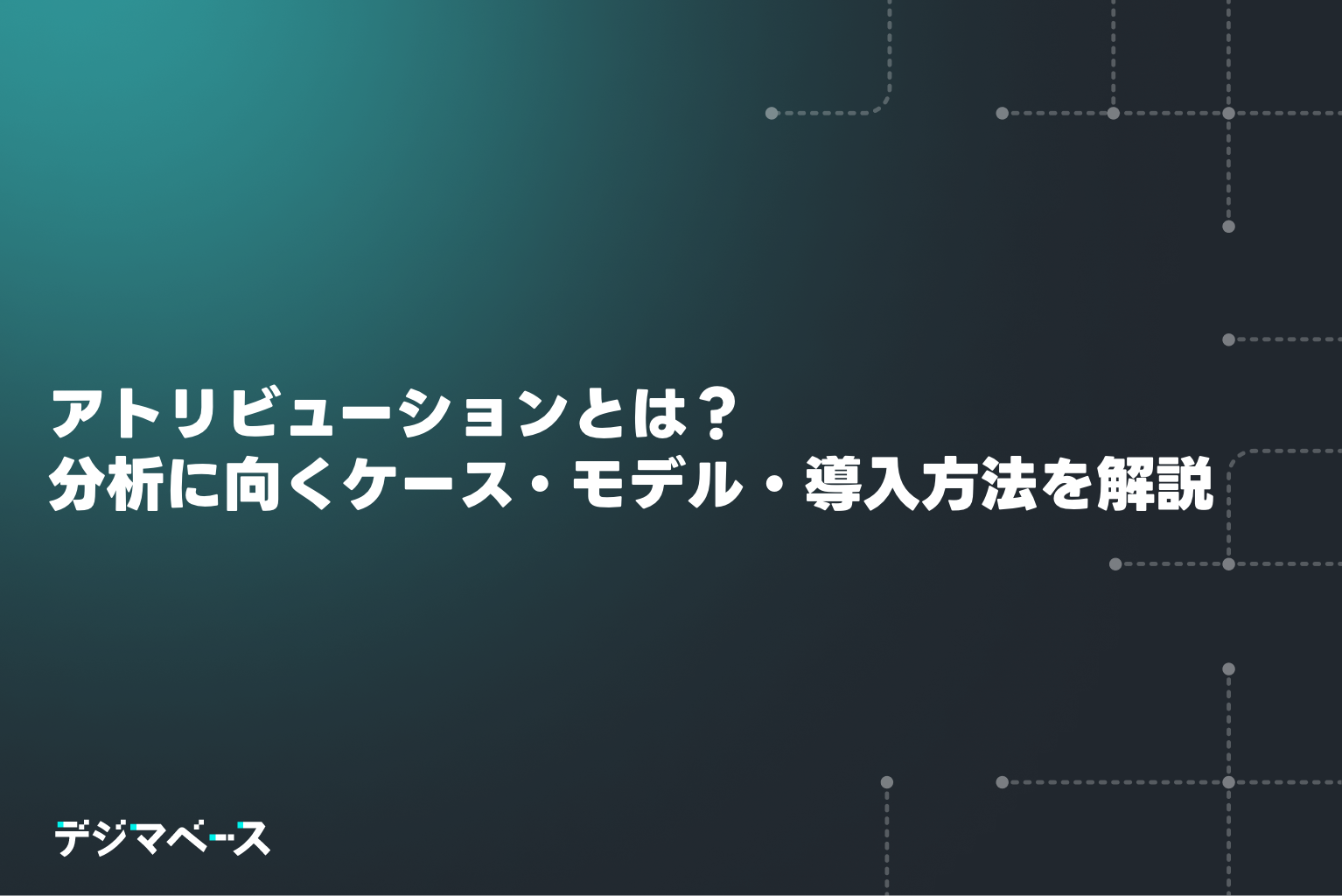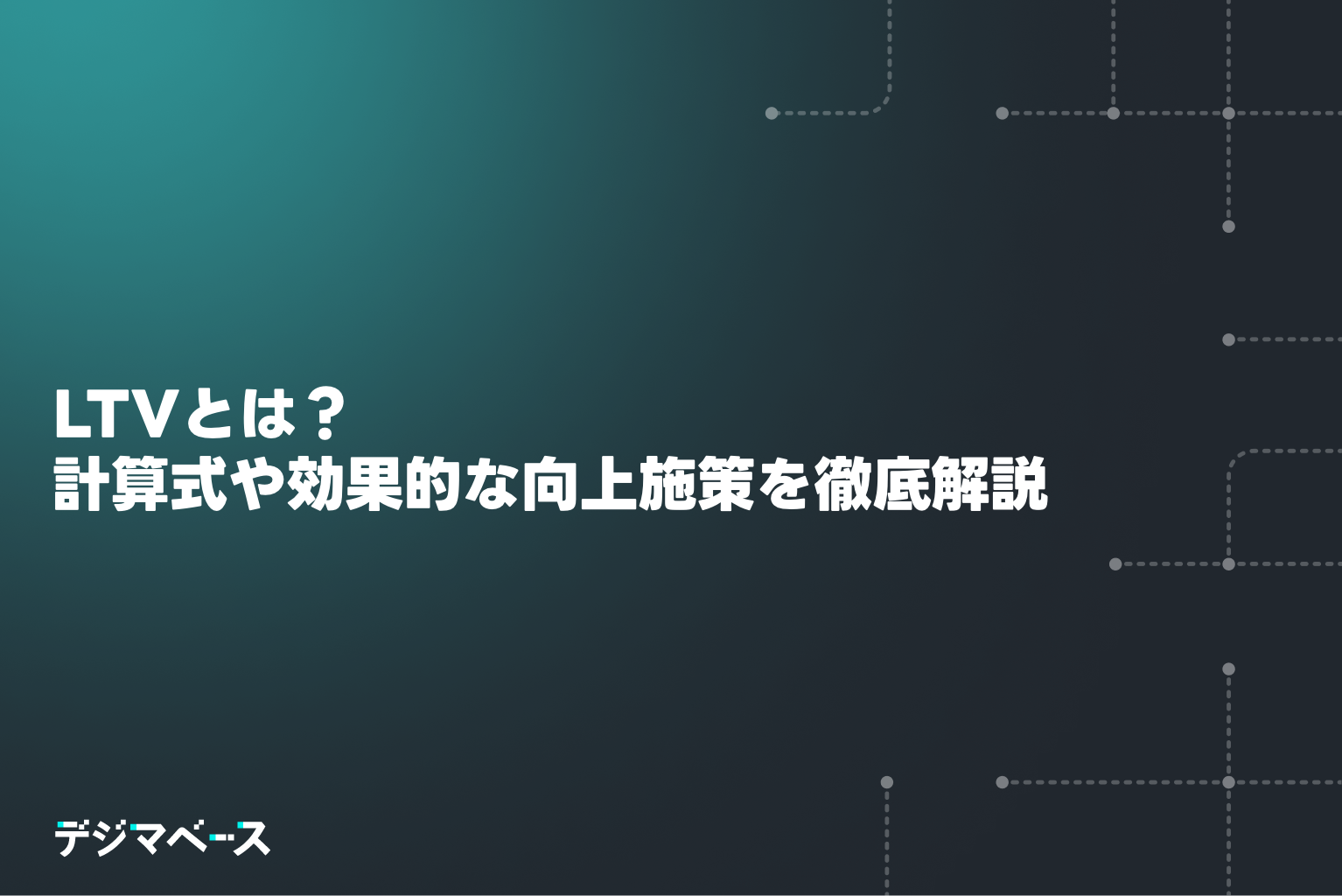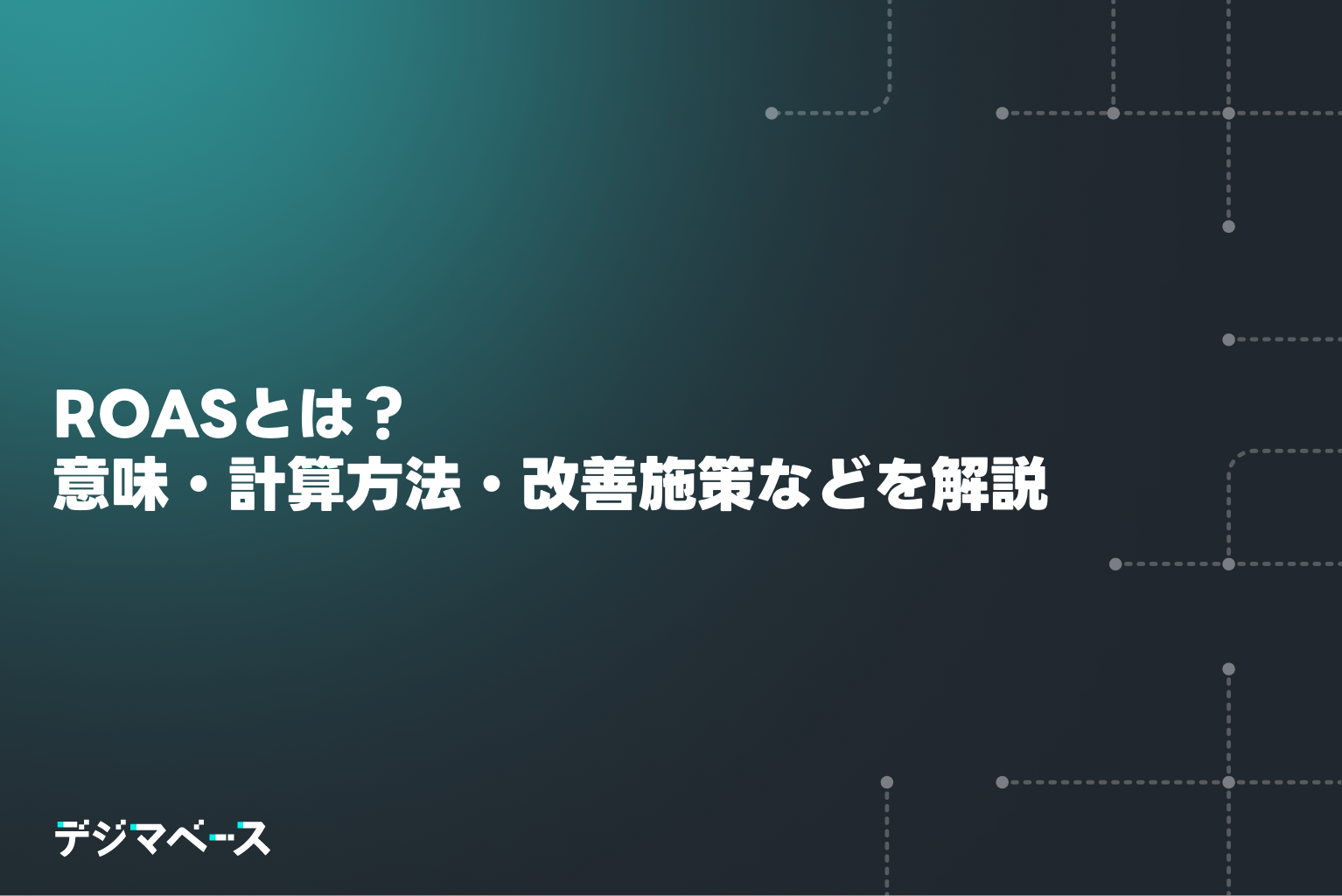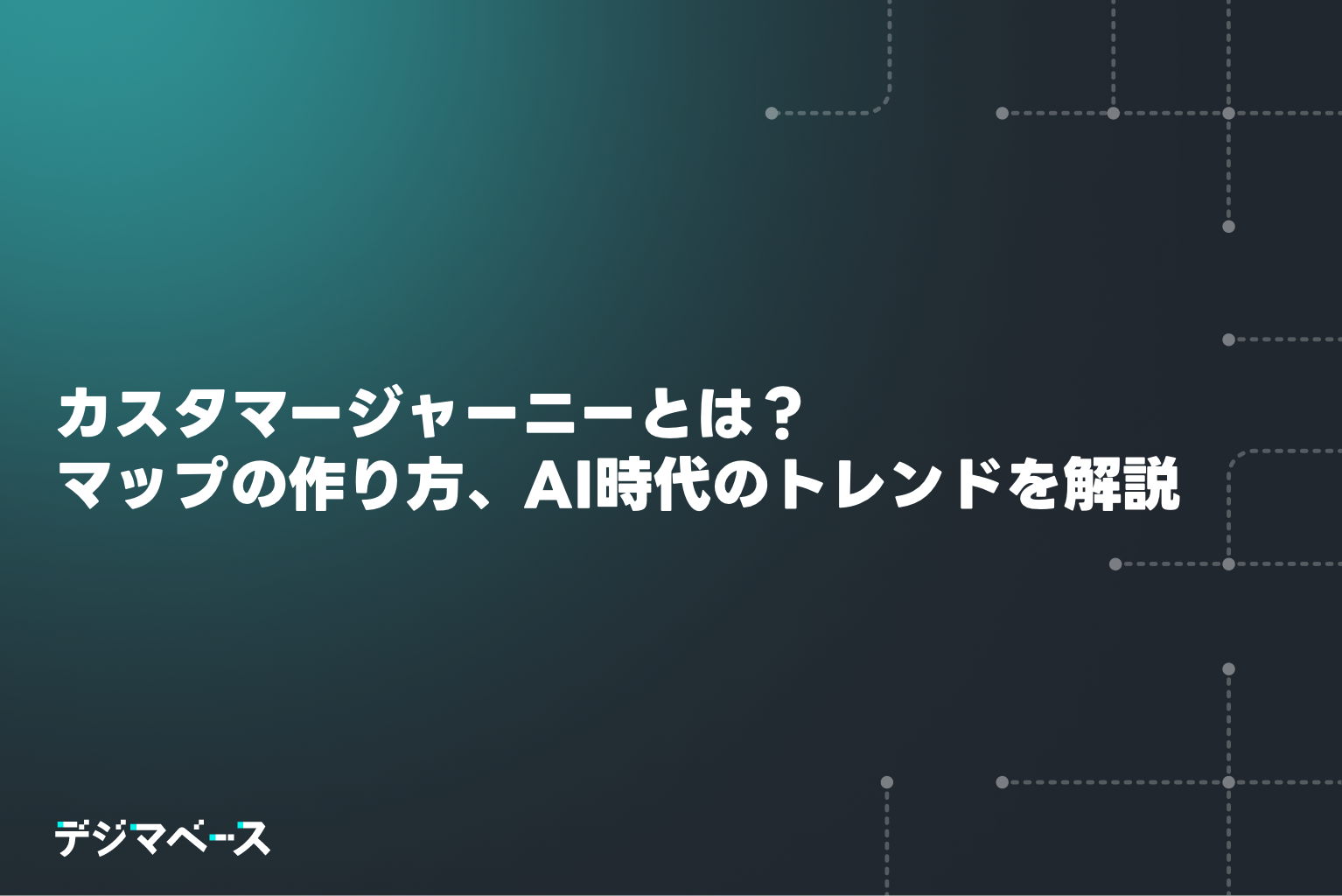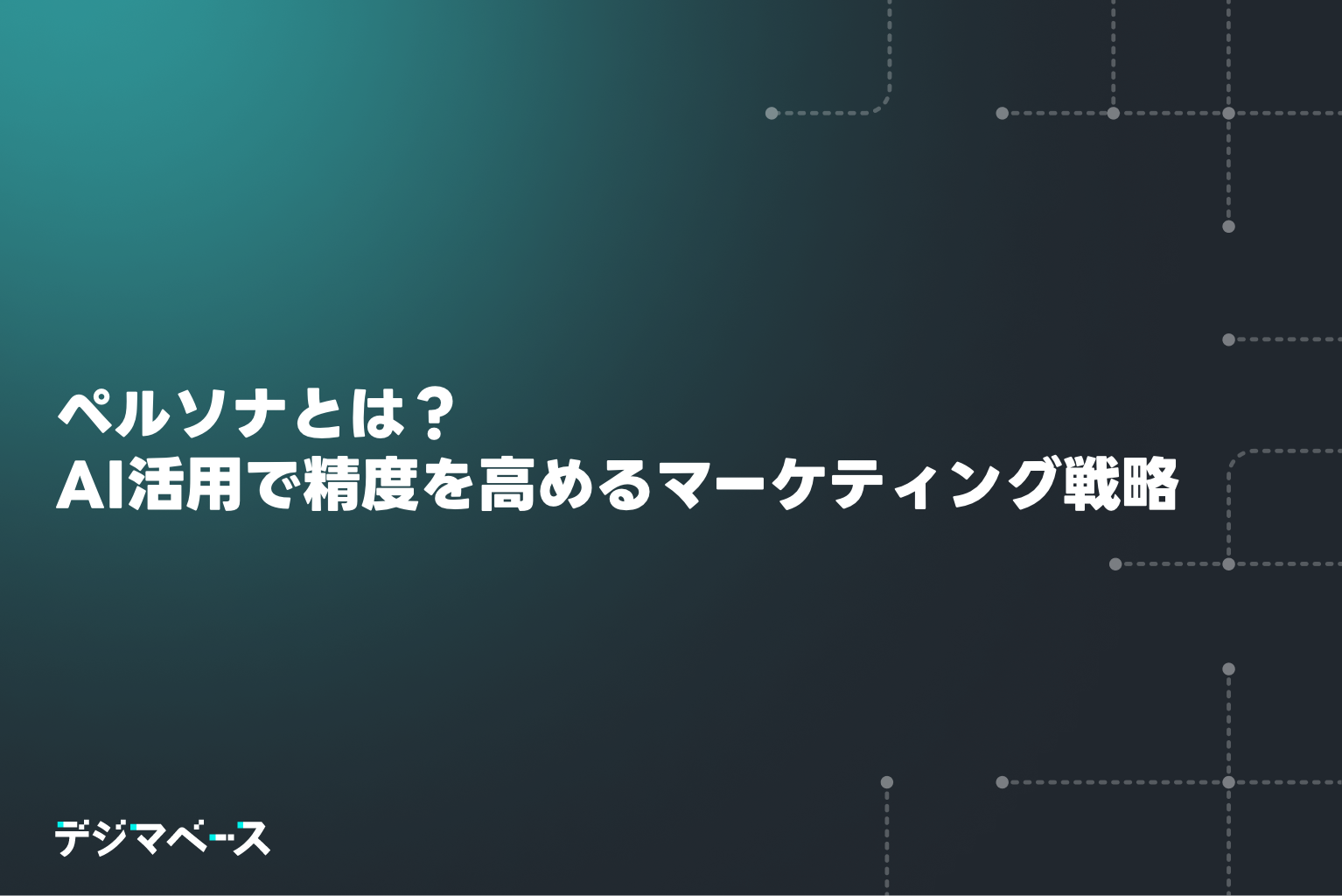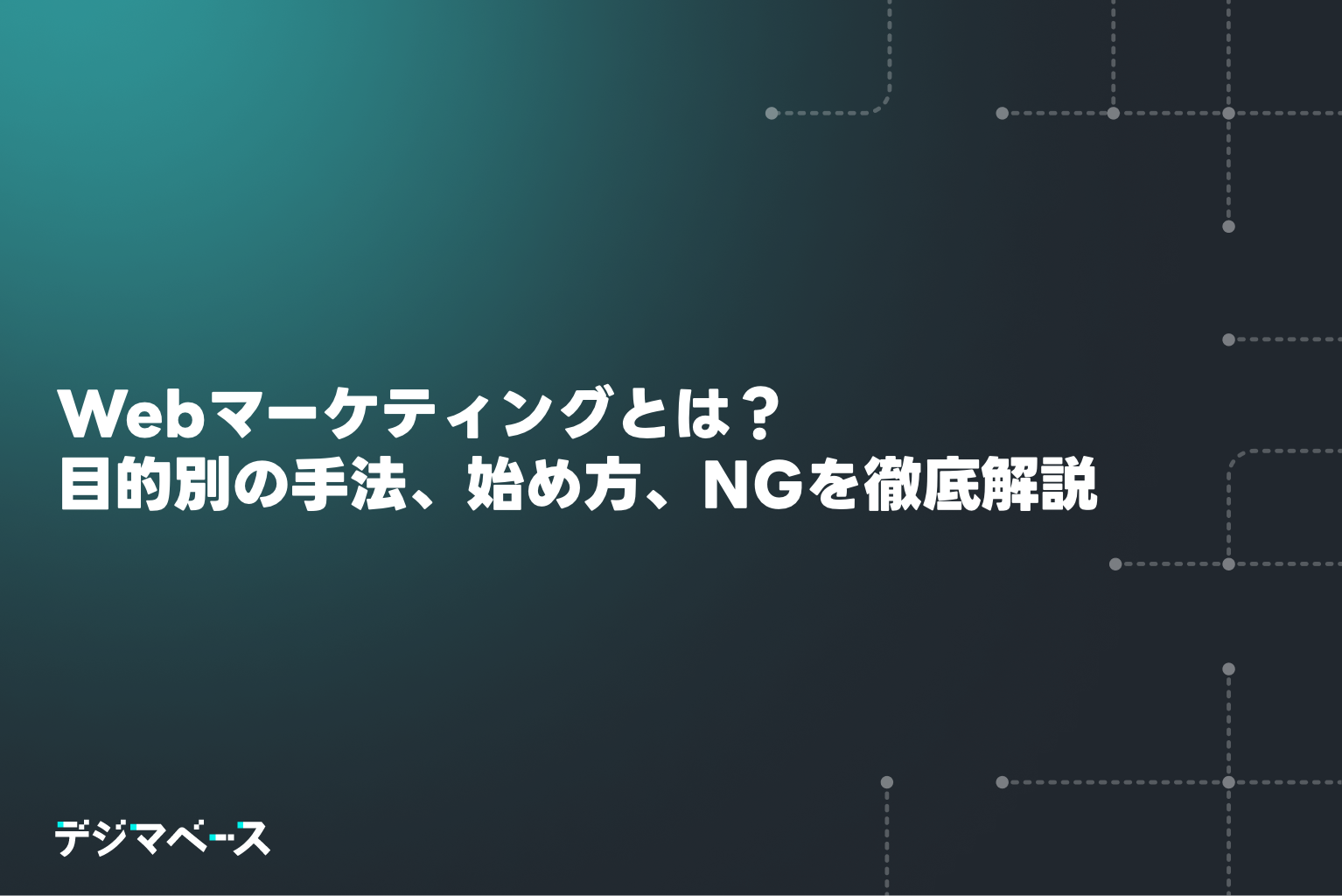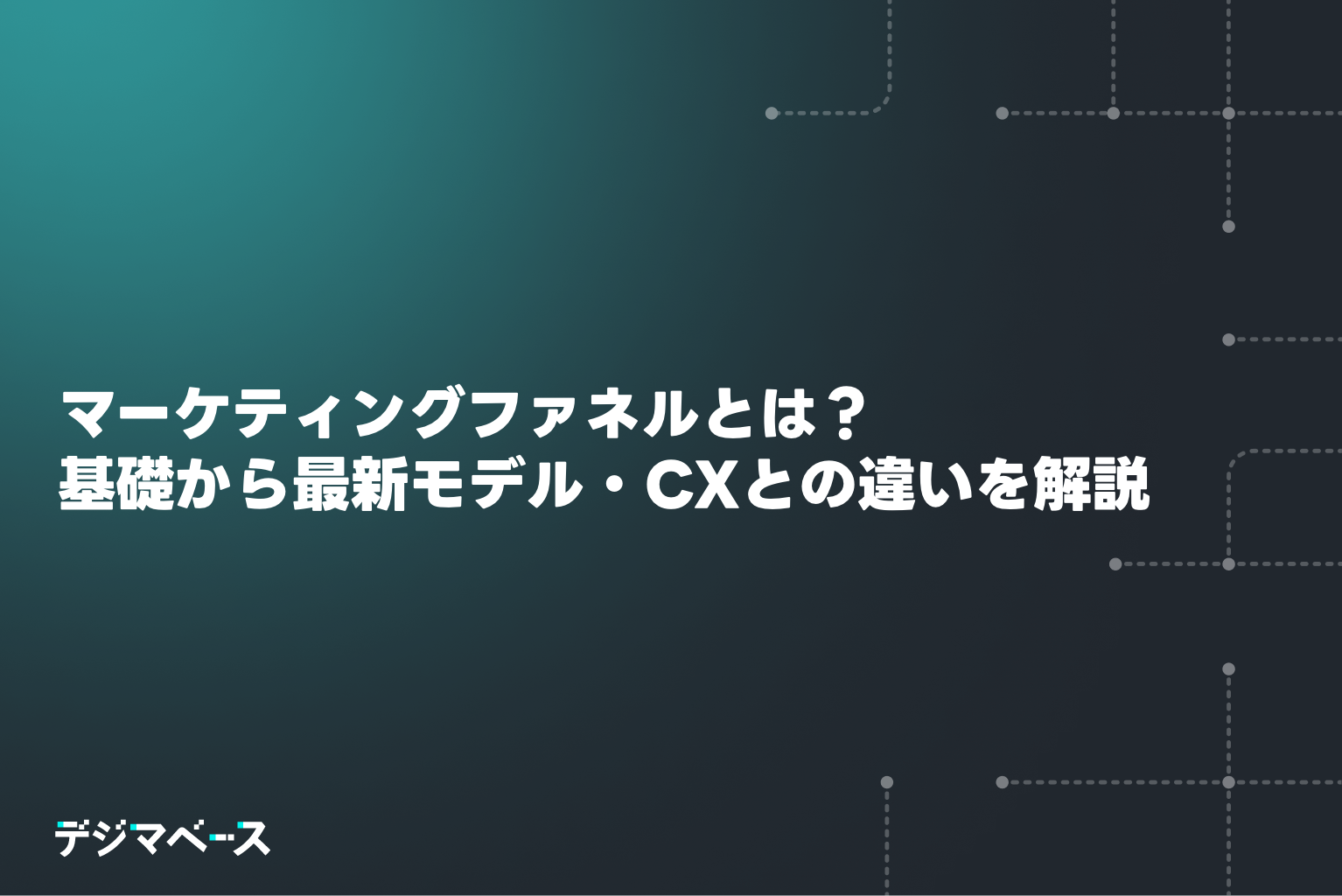
マーケティングファネルとは?基礎から最新モデル・CXとの違いを解説
マーケティングファネルは、顧客が商品やサービスを「認知」してから「購買・リピート」に至るまでの行動プロセスを整理するための基本概念です。
しかし近年、「ファネルはもう古い」との指摘も増えています。デジタル環境の多様化により、顧客行動はもはや一方向ではなく、SNSや口コミを介して循環的に変化しているからです。
本記事では、マーケティングファネルの定義から、AIDA・AISAS・AARRRなどの代表モデル、さらにCX(カスタマーエクスペリエンス)やフライホイールモデルとの違い・関係性までを体系的に解説します
マーケティングファネルの基本概念

この章では、マーケティングファネルの基本的な考え方と構造を体系的に整理します。
ファネルの定義と目的
顧客行動プロセスを可視化する考え方
マーケティングファネルとは、消費者が商品やサービスを「認知」してから「購買」「リピート」に至るまでの行動プロセスを、段階的に示したフレームワークです。
「ファネル(漏斗)」という名称は、多くの潜在顧客の中から実際に購入に至る顧客が徐々に絞り込まれていく様子を表しています。
このモデルを用いることで、企業は顧客がどの段階で離脱しているのか、どのステージに施策を集中すべきかを明確にできます。感覚ではなく、データに基づいた分析的なマーケティング運用を可能にするのが大きな特徴です。
特に現代のデジタルマーケティング環境では、顧客接点は多様化しています。広告、SNS、オウンドメディア、展示会など、どのチャネルが購買に寄与しているかを正確に把握するには、ファネルの視点が不可欠です。
顧客の心理や行動を「認知」「関心」「比較」「購入」などの段階に分けることで、それぞれの課題を定量的に評価し、改善につなげることができます。
なぜファネルがマーケティングに必要なのか
マーケティングファネルが重要な理由は、限られた経営資源を最も効果的に活用するための意思決定をサポートする点にあります。
顧客の購買行動をステージごとに分析することで、広告投資の最適化、見込み顧客の育成効率化、そして顧客獲得単価(CPA)の削減など、経営に直結する改善が可能になります。
主なメリットは次のとおりです。
- ボトルネックの特定:どの段階で顧客が離脱しているかを明確化し、重点施策を設定できる
- 施策の一貫性確保:認知から購買まで一貫した顧客体験(CX=Customer Experience)を設計し、メッセージの整合性を維持できる
- 成果の測定と改善:各段階にKPIを設定し、データドリブンでマーケティングのPDCAを回せる
このようにファネルは、理論ではなく実践のツールです。現場のマーケターや経営者が意思決定を合理化するために欠かせない存在といえるでしょう。
【関連記事】デジタルマーケティングとは?Webマーケティングとの違い、効果的なアプローチを解説
ファネル構造の全体像
認知、興味、検討、購買、リピートの流れ
一般的なマーケティングファネルは、顧客がブランドを知り、興味を持ち、比較・検討を経て購買に至るまでの流れを段階的に表したものです。
近年は、購入後の「リピート」や「ファン化」までを重視するケースも増えています。
| ステージ | 顧客の状態 |
|---|---|
| 認知 | ブランドや商品を初めて知る段階。広告やSNS投稿を通じて露出を増やす。 |
| 興味 | 製品・サービスに関心を示し、情報収集を始める段階。自社サイトやコンテンツで理解促進。 |
| 検討 | 他社製品と比較しながら選定を行う段階。レビューや資料請求などが行動の指標となる。 |
| 購買 | 最終決定を行い、実際に購入行動を起こす段階。購入時の体験やサポート対応が重要。 |
| リピート | 満足度が高ければ再購入や周囲への推奨につながる段階。CRMやロイヤルティ施策が効果的。 |
このように段階ごとに目的と課題が異なるため、企業はそれぞれのステージに対応した戦略的アプローチを取ることが求められます。
各ステージの役割と代表的な施策例
各ファネルでは、企業が取るべきアクションや顧客への関わり方が異なります。それぞれの段階での役割を整理すると、次のようになります。
- 認知段階: 広告、PR、SNS投稿などで潜在顧客にリーチする。動画広告やインフルエンサーマーケティングも効果的
- 興味段階: コンテンツマーケティングやメルマガで情報提供を強化。ホワイトペーパーや無料セミナーも有効
- 検討段階: 比較資料、導入事例、レビューといった信頼性のある情報を提示し、不安を解消する
- 購買段階: ECサイトのUI改善、限定キャンペーン、スムーズな決済プロセスなどで購入を後押し
- リピート段階: 会員特典、ポイント制度、パーソナライズされたフォローアップなどで再購入を促進
重要なのは、これらの施策が単発で終わらず、ファネル全体で有機的につながることです。
例えば、認知段階で獲得したリード(見込み顧客)を興味段階で育成し、検討段階では信頼を強化して購買に導く──このような一連の流れを設計することが、ファネルを最大限に活かす鍵となります。
【関連記事】アトリビューションとは?分析に向くケース・モデル・導入方法まで体系的に解説
マーケティングファネルの主な種類

この章では、マーケティングファネルの代表的なモデルと、デジタル環境における新しい考え方を整理します。従来の理論だけでなく、現代の実践に適した統合的な活用方法を理解することで、効果的なマーケティング設計の全体像を把握できるようになります。
代表的なファネルモデル
AIDA、AISAS、AARRRモデルの特徴
マーケティングファネルを理解するうえで欠かせないのが、AIDA、AISAS、AARRRモデルです。それぞれが異なる時代背景と顧客行動の特徴を反映しており、目的に応じた使い分けが重要です。
まず、AIDAモデルは古典的なマーケティング理論として最も広く知られています。Attention(注意)→Interest(興味)→Desire(欲求)→Action(行動)の4段階で構成され、顧客が商品を認知してから購買に至る心理的プロセスを明確に示します。
次に、AISASモデルはインターネット時代の行動特性を反映した発展形で、Search(検索)とShare(共有)を追加しています。消費者が検索を通じて情報を能動的に集め、購入後にSNSなどで共有する流れを重視しているのが特徴です。
さらに、AARRRモデル(Acquisition/Activation/Retention/Referral/Revenue)は、主にスタートアップやアプリ、SaaSビジネスで活用されるデータドリブン型の成長指標モデルです。顧客獲得から収益化までを数値的に把握し、改善サイクルを高速に回すことができます。
これらのモデルは、活用する文脈によって最適解が異なります。AIDAは広告やブランド育成に、AISASはSNSや検索エンジンマーケティングに、AARRRはオンラインサービスやアプリのグロース施策に適しています。
つまり、ファネルモデルの理解はマーケティング施策の設計思想を支える基盤そのものといえるでしょう。
BtoBとBtoCにおけるファネルの使い分け
同じファネル構造でも、BtoB(企業間取引)とBtoC(一般消費者向け)では、適用の仕方が大きく異なります。
BtoBでは意思決定プロセスが長期化し、複数のステークホルダーが関与するのが特徴です。そのため、各段階で求められる情報や施策が異なります。特にリード獲得から商談化までのプロセスが重視され、MA(マーケティングオートメーション)やCRMを用いたリードナーチャリングが不可欠です。
一方、BtoCでは感情的な要素や瞬発的な購買が中心となり、AIDAやAISASモデルが有効です。SNSを通じた認知拡大や口コミ促進、Eコマースでの購買導線の最適化など、短期間での行動喚起が求められます。
| 区分 | BtoB | BtoC |
|---|---|---|
| 意思決定期間 | 長期(数週間~数か月) | 短期(数分~数日) |
| 主なモデル | AARRR・ファネル型ナーチャリング | AIDA・AISAS |
| 重視される施策 | リード獲得・育成、提案資料の最適化 | 広告・SNS拡散、UX向上 |
| 評価指標 | リード数・CVR・契約率 | CTR・購買率・リピート率 |
このように、BtoBでは信頼構築と継続的な関係の強化、BtoCでは瞬発的なエンゲージメント形成が重要であり、同じファネルでも重視する段階や施策が大きく異なります。
デジタル時代におけるファネルの発展
SNS・SEO・広告を含む統合的ファネル設計
デジタル時代のマーケティングでは、単一のチャネルだけで顧客を獲得することは困難になりつつあります。ユーザーは検索、SNS、動画、オウンドメディアなど、複数の接点を行き来しながら購買に至るため、現代のマーケティングファネルは「チャネル横断的な統合設計」が必須です。
統合的ファネルを設計する際の3つの視点は以下の通りです。
- 接点の統合:SEO・リスティング広告・SNS投稿を連携し、顧客がどこでブランドを認知し、どの経路で検討・購入に至るのかを可視化する
- データ連携の最適化:広告・分析ツールとCRMを統合し、流入経路ごとのLTV(顧客生涯価値)を測定する
- 顧客体験の一貫性:どの媒体でもメッセージやトーンを統一し、ファネルを越えてブランド体験を最適化する
例えば、SNSでの認知施策がSEOコンテンツへの流入を促し、その後リターゲティング広告で検討段階をフォローするような設計は非常に効果的です。このような「統合ファネル思考」は、非線形化した顧客行動に対応するための必須戦略となっています。
フルファネル戦略の考え方
フルファネル戦略とは、認知から購買、さらにはリピート、ロイヤルティー形成までを一貫した視点で最適化するマーケティングアプローチです。
従来のファネルが「購買」で終わっていたのに対し、フルファネルではその後の体験価値と継続利用までを含めて設計します。
これにより、短期的な売上だけでなく、長期的な顧客価値(LTV)の最大化を実現できます。
実践のポイントは次の3点です。
- 上流(認知・興味):ブランディング広告やインフルエンサー施策で潜在層にアプローチ
- 中流(検討・比較):ウェビナー、レビュー、ホワイトペーパーで信頼形成
- 下流(購買・継続):CRMやメールマーケティングで再購入・ファン化を促進
近年では、GoogleやMetaなど主要広告プラットフォームもフルファネル型キャンペーンを推奨しています。
データドリブンで顧客のライフサイクル全体を最適化する動きが加速しており、広告投資の効率化とブランドエクイティの向上を同時に実現できる時代となりました。
【関連記事】LTV(顧客生涯価値)とは?計算式や効果的な向上施策を徹底解説
ファネルは古い?背景と新しい見方
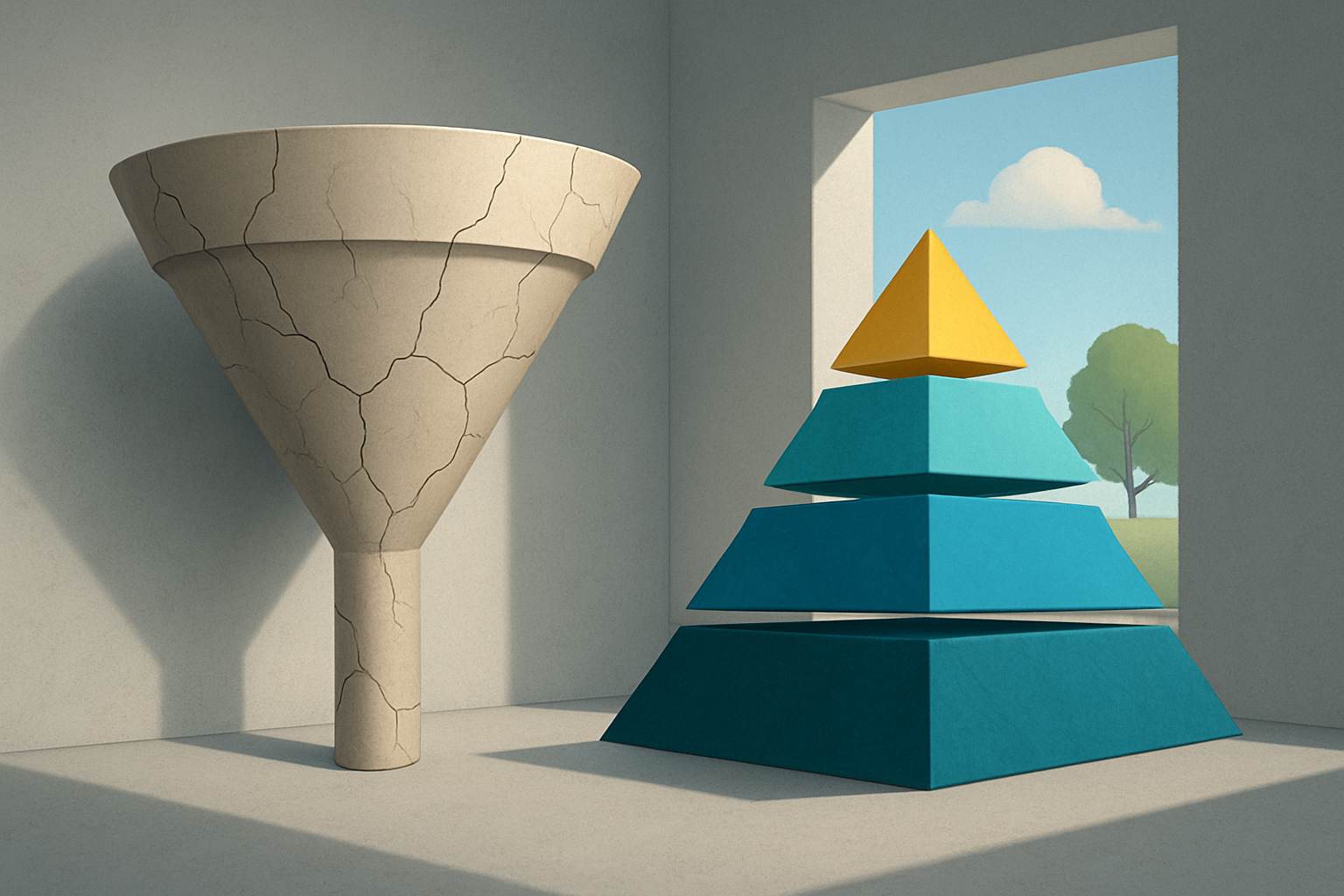
この章では、「マーケティングファネルは古い」と指摘される理由と、その背景にある顧客行動の変化、さらに従来型ファネルの限界について整理します。
「ファネルは古い」と言われる理由
マーケティングファネルが「古い」と言われる最大の理由は、顧客の購買行動がもはや直線的なプロセスでは説明できなくなっている点にあります。
かつては「認知→興味→比較→購買」という順序で進むことが一般的でしたが、デジタル化の進展で顧客接点が多様化し、ブランドへの興味喚起や意思決定の経路が複雑化しました。
SNS、口コミ、動画、検索結果など、あらゆる経路で顧客がブランドに触れるようになった今、購買行動はもはや企業が一方向的にコントロールできるものではありません。
さらに、情報収集手段がマスメディアから、オンラインコンテンツやUGC(ユーザー生成コンテンツ)へと移行したことで、企業発信のメッセージよりも第三者のリアルな声が重視されるようになっています。
この変化により、従来のファネルでは顧客を上から下へと「誘導」する発想が限界を迎えつつあり、より柔軟で双方向的な思考モデルへの転換が求められています。
顧客行動の多様化と非線形プロセス化
現代の顧客は、認知から購買に至るまでの道のりを一方向に進むわけではありません。
例えば、あるユーザーがSNSで商品を見て興味を持ち、口コミサイトで評価を調べ、翌日に比較サイトで価格を確認し、最終的に別のECで購入する――。
このように、購買ジャーニーは“行きつ戻りつ”する非線形なプロセスを描きます。
しかも、情報の主導権は企業ではなく顧客自身にあります。YouTubeのレビューやX(旧Twitter)での投稿が購買判断を左右するケースも多く、同じ商材でも購買経路は顧客ごとに異なります。
こうした環境下では、もはや単一のファネルで顧客行動を完全に可視化することは困難です。企業はファネルを「固定モデル」ではなく、「状況に応じて変化する参考構造」として再定義する必要があります。
SNSと口コミが変えた購買決定の構造
SNSや口コミの台頭は、従来のマーケティングファネルを根底から揺るがしました。これまでの「認知→興味→比較→購買」という流れが当たり前だった時代から、今では口コミが最初の購買トリガーになるケースが珍しくありません。
友人のInstagram投稿を見て即購入したり、TikTokのトレンド商品が数時間で完売する現象がその典型です。また、企業の広告よりもユーザーの体験談が信頼される傾向が強まっています。ネガティブな口コミが購買抑制につながる一方で、ポジティブな投稿はファン層の拡大やUGCの活性化を促進します。
このようにSNSは、ファネルの各段階を横断しながら顧客心理を刺激する存在となり、従来の「縦型モデル」では把握しきれない影響を及ぼしています。
したがって、ファネルを単なる購買導線ではなく、常に双方向のコミュニケーションが生まれる動的な構造として捉える必要があります。
従来型ファネルの限界
従来型のマーケティングファネルは、企業から顧客へメッセージを伝え、購買へと導く一方通行型モデルを前提にしています。
しかし現在の市場環境では、購買後の体験やロイヤルティー形成、ファン化プロセスが競争優位を左右します。オンラインとオフラインが融合した今、一度の購買で終わる顧客関係を前提にした設計では、LTVの最大化は見込めません。
そのため、多くの企業が従来のファネルを補完する形で、循環型・継続型のフレームワーク(例:AARRRモデルやCX設計)を導入し始めています。
ファネル自体は依然として有用な分析ツールですが、それ単体では顧客体験や再購入施策を表現しきれないのです。
リピート・ファンを想定しにくい構造の問題
もともとファネルは「新規顧客の獲得」を目的としたモデルであり、購買後のリピート行動やファン化を想定していません。そのため、次のような課題が生じやすくなります。
- リテンション(顧客維持)や再購入施策がファネル外に置かれ、戦略に反映しにくい
- 口コミ・紹介など、ロイヤルティ経由の新規流入を可視化できない
- LTV重視の現代マーケティングに適合しづらい
こうした背景から、企業はファネルの「出口」ではなく「循環」を意識した設計が求められています。すなわち、購買後のブランド体験や顧客との関係構築をファネルの延長線上に置く発想が重要なのです。
顧客体験を反映できない課題
従来型のファネルには、もう一つ大きな限界があります。それは、顧客体験を定量的に表現できない点です。
ファネルは行動プロセスを定義する一方で、顧客がその過程で何を感じ、どの程度満足しているかを測ることはできません。
例えば、同じ「検討」段階にいる顧客でも、ブランドへの信頼度や期待値は大きく異なります。こうした心理的要素を無視したままでは、最適なコミュニケーション設計は困難です。
そのため、近年ではファネルの概念をCX指標(NPSやCSATなど)と統合し、定量+定性のハイブリッドモデルとして再構築する動きが広がっています。
顧客中心の時代においては、行動データだけでなく、感情・満足・体験を含めて分析することが、真の「ファネル理解」へとつながるのです。
ファネルに代わる新しいマーケティング思考
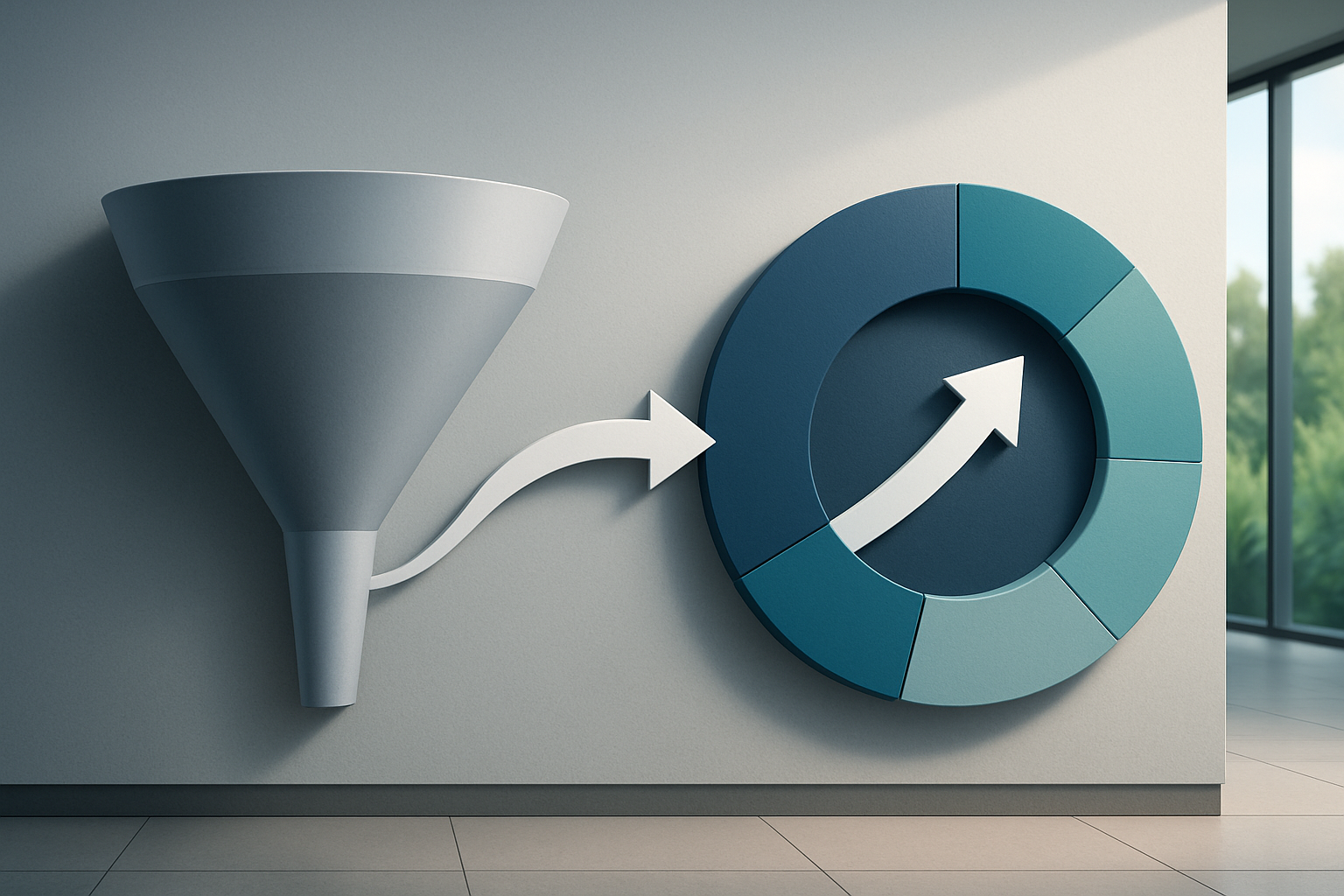
この章では、従来のマーケティングファネルに代わる新しい思考法として、フライホイールモデルとCXフレームワークを取り上げます。
フライホイールモデルの登場
フライホイールモデルは、従来のファネル型思考が抱えていた「顧客獲得で終わる構造」を打破し、顧客を中心に据えたサイクル型マーケティングを提唱する新しい概念です。
その名の通り、円盤(ホイール)が回り続けるように、顧客満足度の向上とリピートが企業成長を自動的に加速させるという思想に基づいています。
このモデルでは、購入後の体験やサポート、口コミなど、顧客との“その後の関係性”が重要な役割を果たします。つまり、顧客を「再びファネルに戻す」よりも、「ファネルの外に出さない」状態を理想とするのです。
特にSaaSやサブスクリプション型のビジネスでは、顧客との継続的な関係こそが収益の持続性を左右するため、フライホイールはより現実的なモデルとして注目を集めています。
この発想の中核には、マーケティング・営業・カスタマーサクセスの三部門が一体となり、顧客を中心に推進力を生み出す組織構造を築くという考え方があります。それこそが、次世代のマーケティングにおける成長戦略の要といえるでしょう。
顧客体験を中心に循環させる仕組み
フライホイールの最大の特徴は、顧客体験を成長のエンジンとして扱う点にあります。
従来は広告やキャンペーンによって新規顧客の獲得を目指していましたが、フライホイールでは「既存顧客の良質な体験」こそが新たな顧客を呼び込む構造を生み出します。
具体的には、次の3つの取り組みが重要です。
- サポート品質の向上:問題解決までのスピードと満足度をモニタリングし、継続的に改善する
- コミュニティ形成:顧客同士やブランドとの交流を促進し、ファン層を育成する
- 顧客の成功支援:製品を“売る”のではなく、顧客が“成果を得る”まで伴走する
このように、フライホイールは単なるマーケティング手法ではなく、企業文化を顧客中心へ転換する思考モデルでもあります。顧客体験が好循環すれば、ブランドへの信頼が推進力となり、ビジネス全体が自律的に回り続けるのです。
継続的エンゲージメント強化の重要性
フライホイールモデルにおいて、最も重要なキーワードは「継続的エンゲージメント」です。なぜなら、顧客との関係が続くほど、信頼とロイヤルティーが高まり、企業の成長速度も加速するからです。
そのためには、購買後のコミュニケーションを絶やさず、価値提供の一貫性を保つことが欠かせません。効果的な施策の例としては次のようなものがあります。
- 定期的なアップデート共有や限定コンテンツで関心を維持する
- カスタマーサクセスチームが顧客の成果を伴走支援する
- レビューやNPS(ネットプロモータースコア)を通じて顧客の声を収集し、改善に反映する
このように、エンゲージメントの連続的な強化は、LTV向上と離脱率の低下を同時に実現します。
顧客接点を途切れさせないこと、それ自体がフライホイールを止めないエネルギーとなるのです。
CXフレームワーク
CX(カスタマーエクスペリエンス=顧客体験)フレームワークとは、顧客がブランドと接するあらゆる瞬間を「一貫した体験」として設計・最適化する考え方です。
重要なのは、単なるサービスの良し悪しではなく、「顧客がどう感じたか」を可視化し、データとして扱う点にあります。
顧客体験の重要性は、機能や価格だけで差別化が難しくなった現代において、感情的な価値が購買行動を決めるようになったことにあります。
そのため、企業はマーケティング・営業・サポートの各部門を横断し、顧客の期待に応える統合的な体験設計を行う必要があります。
代表的なCX向上の施策としては、以下が挙げられます。
- 問い合わせへの迅速な対応と丁寧なフォローアップ
- パーソナライズされたサービス提案
- カスタマーサポートとコミュニティ運営の両立
顧客体験を重視する企業では、結果としてリピート率や紹介率が向上し、ブランド信頼資産の積み上げが進みます。
顧客体験価値を測定・最適化する考え方
CXを成功させるためには、感覚的な判断に頼らず、データに基づく定量的評価を行うことが不可欠です。
代表的な指標には、次のようなものがあります。
- NPS(ネットプロモータースコア):顧客がブランドを他者に推奨する意向を数値化
- CSAT(顧客満足度):サービス利用直後の満足度を即時に測定
- CES(顧客努力指数):課題解決に要した労力を可視化し、利便性を評価
これらの指標をもとに顧客の声を分析し、改善施策を継続的に実行することでCXを進化させます。
さらに、UXデザインやパーソナライゼーションと組み合わせることで、体験を個別最適化できます。
つまり、CXとは「感情価値を科学的にマネジメントする仕組み」であり、感性とデータの両立こそが企業成長の鍵となるのです。
ファネルとの補完的な関係性
CXはファネルの対立概念ではなく、補完的な関係にあります
ファネルが顧客獲得の「流れ(プロセス)」を示すのに対し、CXはその流れ全体を「質(体験)」の面から支える役割を担います。
例えば、認知段階ではポジティブな第一印象を設計し、検討段階では不安を払拭するUXを提供し、購買段階ではスムーズな手続きと安心感を保証する――。こうした段階ごとの体験品質が、最終的なコンバージョン率とLTVを左右します。
実務的には、ファネル上の各KPIとCX指標(NPS・CSATなど)を連動させ、どのステージで体験が阻害されているのかを特定するのが有効です。
こうしてファネルをエクスペリエンス中心型へと進化させることで、企業は量的成果と質的価値を同時に最大化できます。
よくある質問(FAQ)
この章では、マーケティングファネルに関して多くの実務担当者が抱く疑問を整理し、理解をより深めるためのポイントをFAQ形式で解説します。
Q1. マーケティングファネルとカスタマージャーニーの違いは?
マーケティングファネルとカスタマージャーニーは、どちらも顧客行動を整理する代表的なフレームワークですが、焦点と用途に明確な違いがあります。
ファネルは主に、購買に向けた行動変化を企業側の視点で段階的に分析するモデルです。「認知 → 興味 → 検討 → 購買」という流れの中で、各段階の離脱率やCVR(コンバージョン率)を可視化し、施策の最適化に役立てます。
例えば、興味段階で離脱が多い場合は、訴求内容や導線設計を改善するといった判断が可能です。つまりファネルは、数値でマーケティングを管理するための構造といえます。
一方、カスタマージャーニーは顧客視点を中心に据えた体験マッピング手法です。
「どんなきっかけや感情で購買や再利用に至るのか」を時系列で描き、体験設計やUX(ユーザー体験)改善の文脈で使われます。
共感マップやCX評価(顧客体験評価)と併用されることも多く、ファネルよりも定性的な理解に強みがあります。
つまり、
ファネル=企業視点での行動管理モデル
カスタマージャーニー=顧客視点での体験設計モデル
という棲み分けです。
両者を組み合わせることで、数値と感情の両側面からマーケティングを立体的に設計できるようになります。
Q2. ファネルは今後も使われ続けるの?
結論から言えば、マーケティングファネルは今後も有効な概念として使われ続けます。
ただし、その形はこれまでの「一方向」「直線的」構造から、より柔軟で循環型のモデルへと進化していくでしょう。
現代ではSNSやレビューサイトの普及によって、顧客の購買行動が複雑化しています。一度離脱した顧客が、数週間後に口コミやリターゲティング広告をきっかけに再エンゲージする──そんなケースも珍しくありません。
このような背景から、ファネルを「顧客の意識段階を可視化するツール」として再定義し、フライホイールモデルやCXフレームワークと組み合わせて活用する流れが主流になっています。
さらに、デジタル技術の発展により、MAツールやCRM、広告配信データを統合してファネル各層の成果をリアルタイムで検証できるようになりました。
AIによるスコアリングやパーソナライズ施策も進化し、ファネルの運用はより高度かつ動的なものになっています。
つまりファネルは、もはや“過去の理論”ではなく、データドリブン時代のマーケティング基盤として再定義され続けている概念なのです。
Q3. 初心者がマーケティングファネルを学ぶ際のおすすめ手順は?
マーケティングファネルを初めて学ぶ場合は、理論から入るよりも自分の購買体験をもとに考えることから始めるのが効果的です。
「自分はどんなきっかけで商品を知り、どの瞬間に購買を決めたのか?」というプロセスを観察すると、自然とファネルの構造が見えてきます。
そのうえで、以下のステップを踏むのがおすすめです。
- 基本モデルを理解する
AIDA・AISAS・AARRRなど、主要なファネルモデルを比較し、それぞれの段階の意味を押さえる。 - 小さなファネルを自作してみる
実際のサービスや自社データを使い、簡単なファネル図を手書きで描いてみる。
例:訪問数 → 資料請求数 → 商談数 → 成約数。 - データ分析を試す
Web解析ツール(例:Googleアナリティクス)でユーザー行動を可視化し、広告・メール施策ごとのコンバージョン率を比較してみる。 - 小規模な改善実験を行う
離脱率が高い段階を1つ選び、LP改善やCTA最適化などの施策を実施。結果を数値で検証する。
このように、ファネルを“仮説と検証のフレームワーク”として使い続けることで、理解が深まり実践力が磨かれます。ファネルは一度作って終わりではなく、企業の成長や市場変化に合わせて磨き続ける「進化型設計図」なのです。
Related Articles